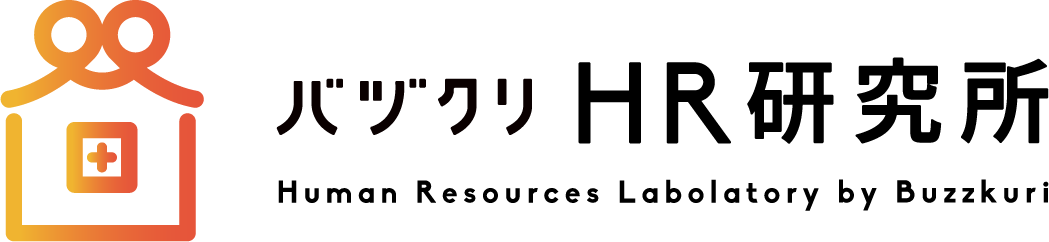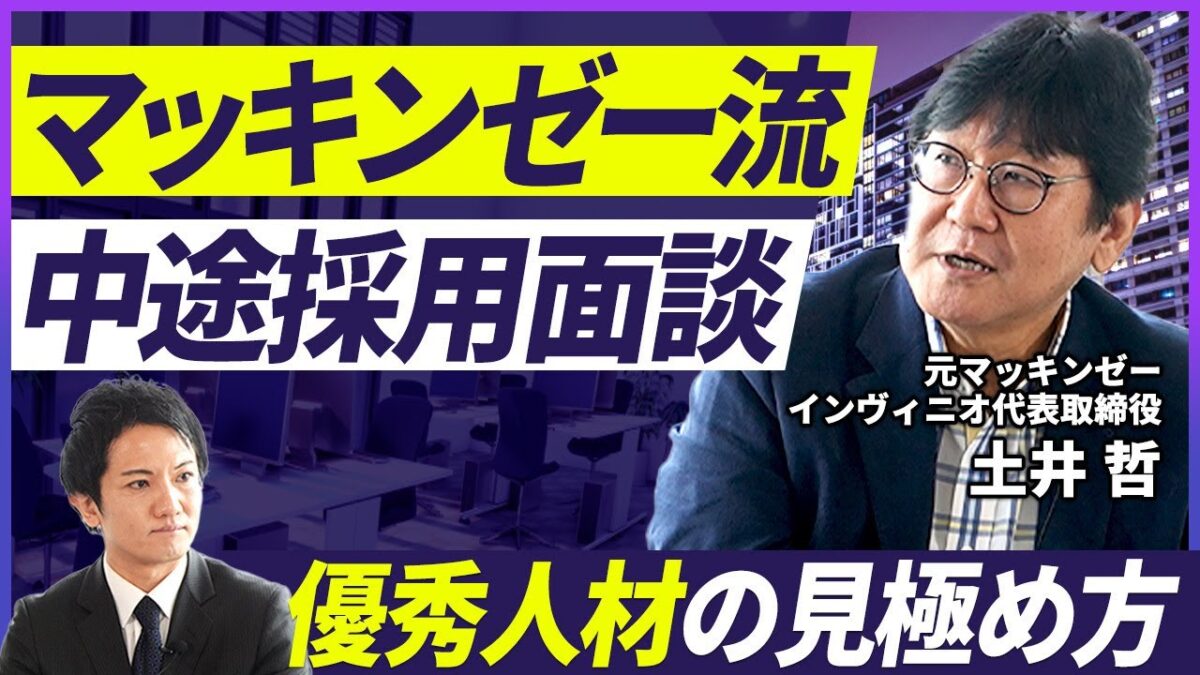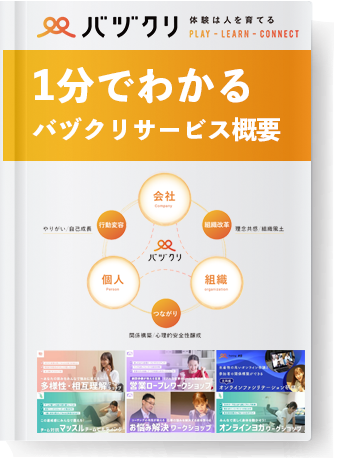目次
はじめに
誰しも「窓際社員」と呼ばれることは避けたいものです。しかし現実には、長年の経験を持つベテラン社員が、変化の速い時代の中で力を発揮できず、活躍の場を失ってしまうケースが少なくありません。
特に大きな転機となるのが45歳以降のキャリアです。かつては「会社がキャリアを決めてくれる」時代でしたが、今はそうではありません。AIやDXの進展、働き方改革、多様な価値観の浸透などによって、社員一人ひとりが主体的にキャリアを描く必要性が高まっています。
本記事では、人材育成・組織開発の専門家である株式会社インヴィニオ代表 土井哲氏とバヅクリ株式会社代表取締役 佐藤太一氏の対談を整理し、読みやすくまとめました。
なお、前編では「ベテラン社員のパフォーマンス低下とその対策」「組織における役割」「窓際社員が生まれる原因」について詳しく取り上げています。まだご覧になっていない方は、ぜひそちらからお読みください。
本記事ではその後編として、以下のポイントをご紹介します。
- 45歳以降のキャリアプランの考え方
- 窓際社員予備軍を採用・配置の段階で見抜く方法
- 組織と個人がともに変化するためのヒント
これからの時代、ミドル・シニア層をどう活かすかは、企業にとって避けて通れない課題です。ぜひ人材戦略のヒントとしてご活用ください。
45歳以降のキャリアプラン
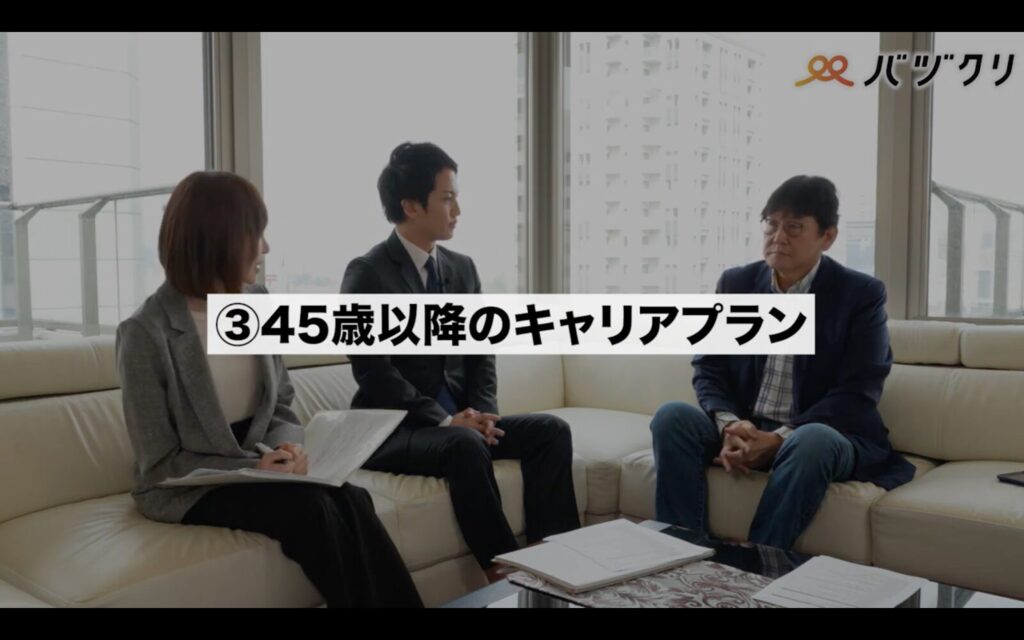
① マインドセットの転換
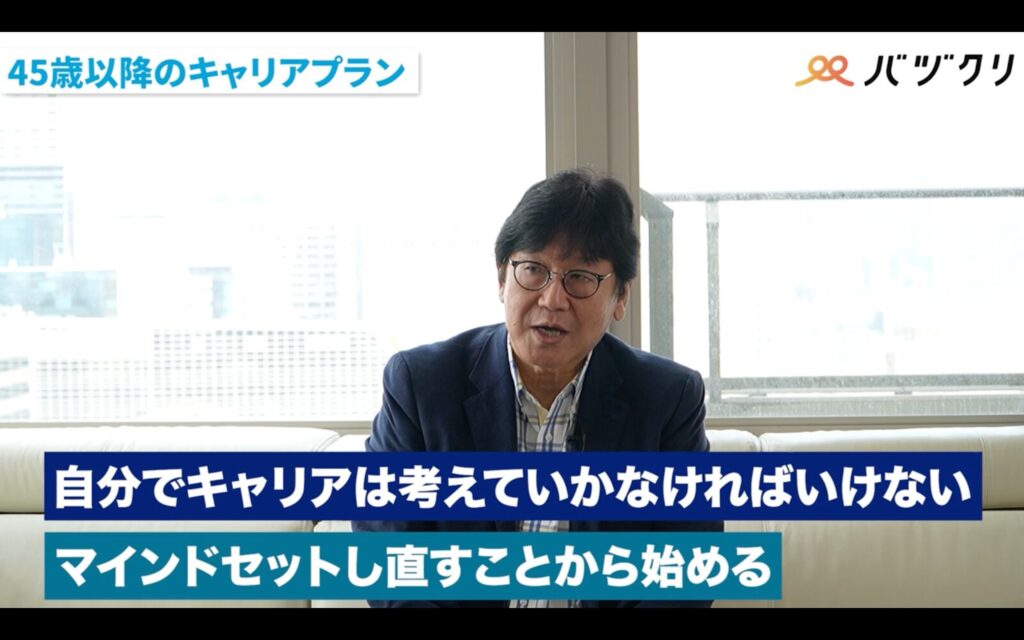
かつては「会社がキャリアを決めてくれる」時代がありました。配置転換や昇進の機会が与えられ、それに従ってキャリアを積んでいく。そんな受け身のスタイルが一般的でした。
しかし、変化のスピードが激しい現在、同じ考え方のままでは通用しません。AIやDXの普及、ダイバーシティの推進、働き方改革などによって、一人ひとりが主体的にキャリアを描いていくことが求められています。
特に45歳以降は、これまでの経験を活かしながらも「これからどう学び直すか」「どんな役割で貢献できるか」を自ら考えることが必要です。役職や年齢に頼るのではなく、変化に適応する力そのものが問われるのです。
つまり、これからのキャリア形成の第一歩は、「会社任せではなく、自分の未来を自分で設計する」意識への転換にあります。
② スキル・経験の棚卸し
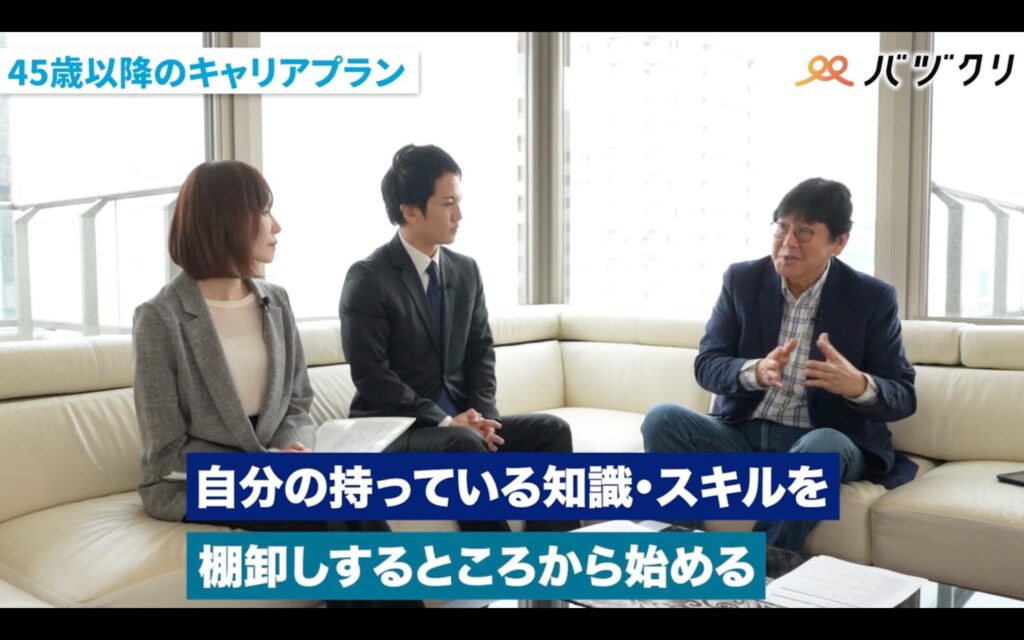
マインドセットを切り替えた次のステップは、自分の持っているスキルや経験を客観的に整理することです。
長年のキャリアの中で培った知識やスキルには、これからの時代に活きるものもあれば、残念ながらすでに価値が薄れてしまったものもあります。まずはその「棚卸し」を行い、次の3つに分けて考えることが重要です。
- これからも活かせる強み
例:特定業界に関する深い知見、マネジメント経験、人脈など - 価値が下がりつつあるスキル
例:過去の成功体験に基づく旧来型の営業手法や、デジタル化に対応していない知識 - 不足している新しいスキル
例:デジタルリテラシー、リモート環境でのマネジメント力、多様な人材との協働スキル
特に45歳以降は「強みをどのように伸ばすか」と同時に、「不足部分をどのように補うか」を明確にする必要があります。
そのためには、上司や人事部との対話だけでなく、自分自身が棚卸し結果をもとにキャリアビジョンを描く姿勢が欠かせません。企業側も、こうした棚卸しを支援する仕組みを提供することで、ベテラン社員の再活躍を後押しできます。
③ 戦略とスキルの紐づけ
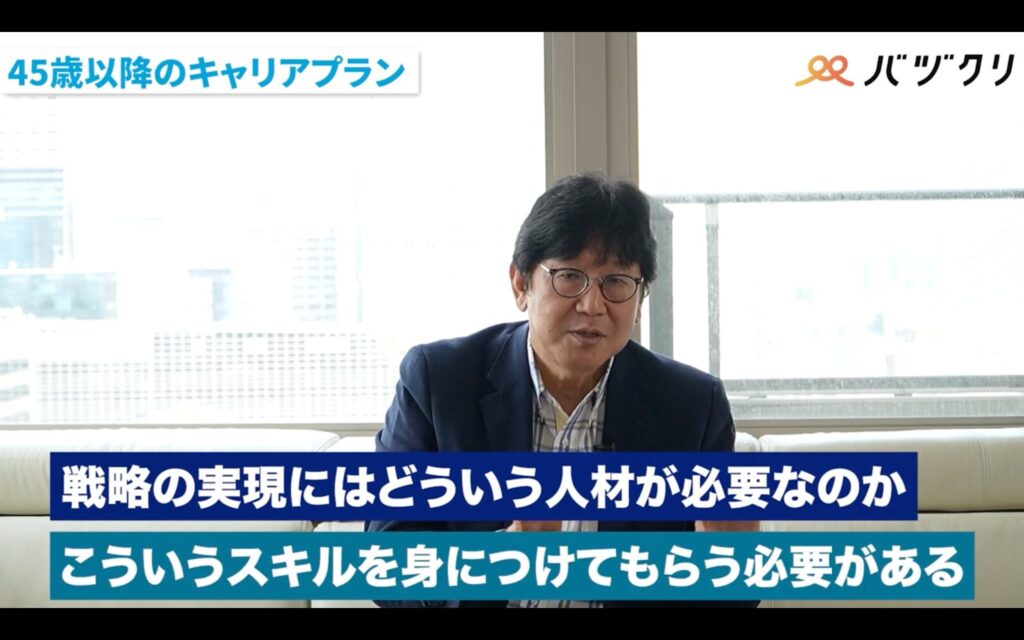
スキルの習得としてリスキリングが注目されていますが、見落とされがちなのが、学び直しと経営戦略の関係性です。
多くの企業では「AIを学ぼう」「DX人材を増やそう」といった具合に、流行のスキルを学ばせる取り組みが先行しがちです。しかし、それでは学びが断片的になり、実務や事業成果につながらないケースが少なくありません。
重要なのは、まず「自社の戦略を実現するために、どんな人物像が必要か」を明確にすることです。そして、その人物像に求められるスキルを逆算し、学びの指針として提示する必要があります。
こうしたプロセスを経ることで、社員のキャリア形成と組織の成長が直結します。リスキリングが単なる知識習得に終わらず、戦略実現のための投資として機能するのです。
④ リスキリングの本質を理解する
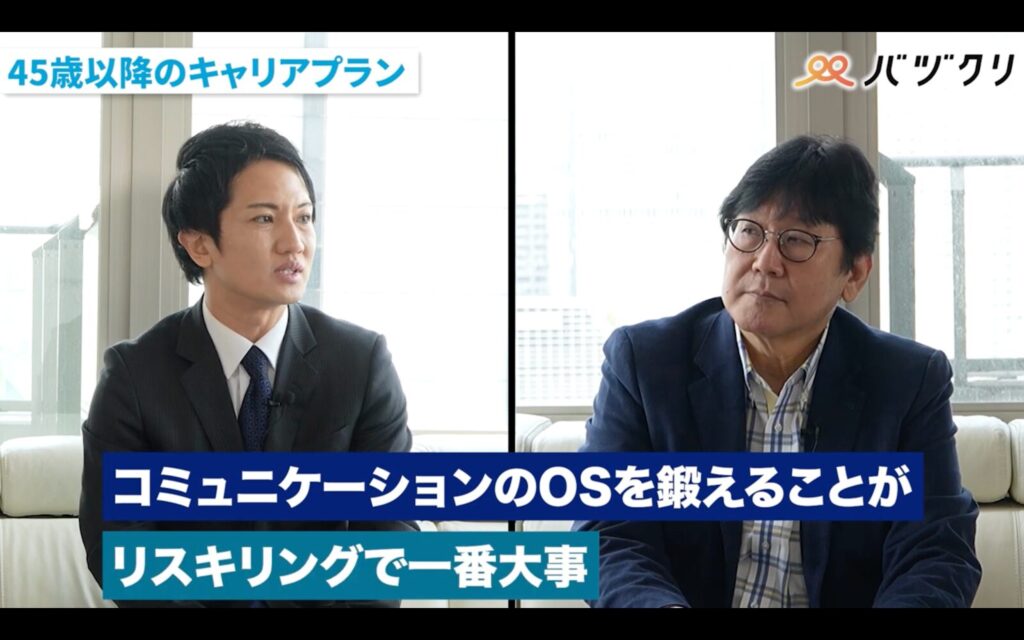
戦略とスキルの方向性を明確にしたうえで、次に必要になるのが「リスキリング=学び直し」です。
しかし、ここで誤解されやすいのが「新しい知識を学べば十分」という発想です。
確かにAIやDXといった先端領域のスキルは重要ですが、それ以上に問われるのは、それを活かすための“OS”=コミュニケーション力やマインドセットです。
いくら最新の知識を学んでも、それをチームに浸透させたり、部下を動かす力がなければ成果にはつながりません。相手の立場を理解し、信頼関係を築いたうえで初めてスキルは活きてきます。
リスキリングの本質は、スキルと人との関わり方を両輪で強化することにあります。
工場長が変わったシステムコーチングの事例
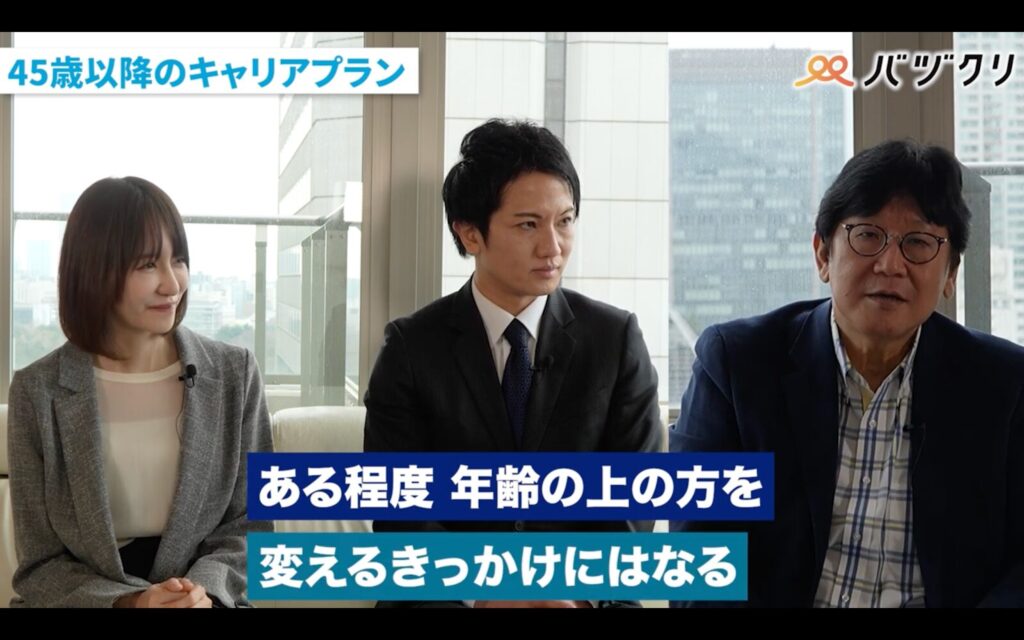
ある製造業の工場では、現場のコミュニケーションが課題となっていました。そこで導入されたのが「システムコーチング」と呼ばれる手法です。個人への1対1指導ではなく、チーム全体で人間関係を改善していくアプローチでした。
当初、工場長は「なぜこんなことをやる必要があるのか」と懐疑的で、表情も硬かったといいます。しかし、半年間取り組んでいく中で、チームメンバーとあだ名で呼び合うようになり、対話も増加。次第に表情が柔らかくなり、現場全体の雰囲気も大きく変化しました。
この事例が示すのは、どんなに経験豊富なベテランであっても、コミュニケーションとマインドを変えることで再び活躍できるということです。リスキリングの本質は単なる知識習得ではなく、土台となる“人との関わり方をアップデートする取り組み”でもあるのです。
研修での取り組み例:失敗を共有して学び合う
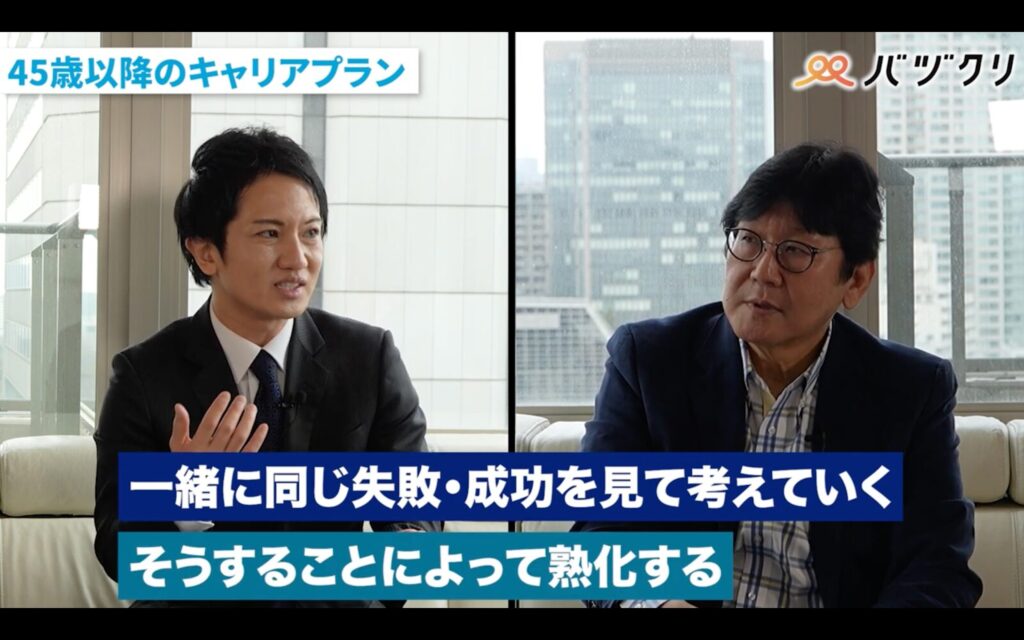
さらに効果的なのが、「失敗を共有する研修」です。
参加者が自らの失敗体験をオープンに語り合うことで、「自分だけではない」という安心感が生まれ、心理的安全性が高まります。
単に失敗を並べるのではなく、優先度の高い課題を選び、解決策をディスカッションする仕組みを組み込むことで、実践的な学びにつながります。
この取り組みはベテラン社員にとって「経験を語ること自体が組織貢献になる」という意識の転換を促し、リスキリングを「知識習得」から「学び合いの文化」へと拡張させます。
④ ロールモデルの不在と多様化
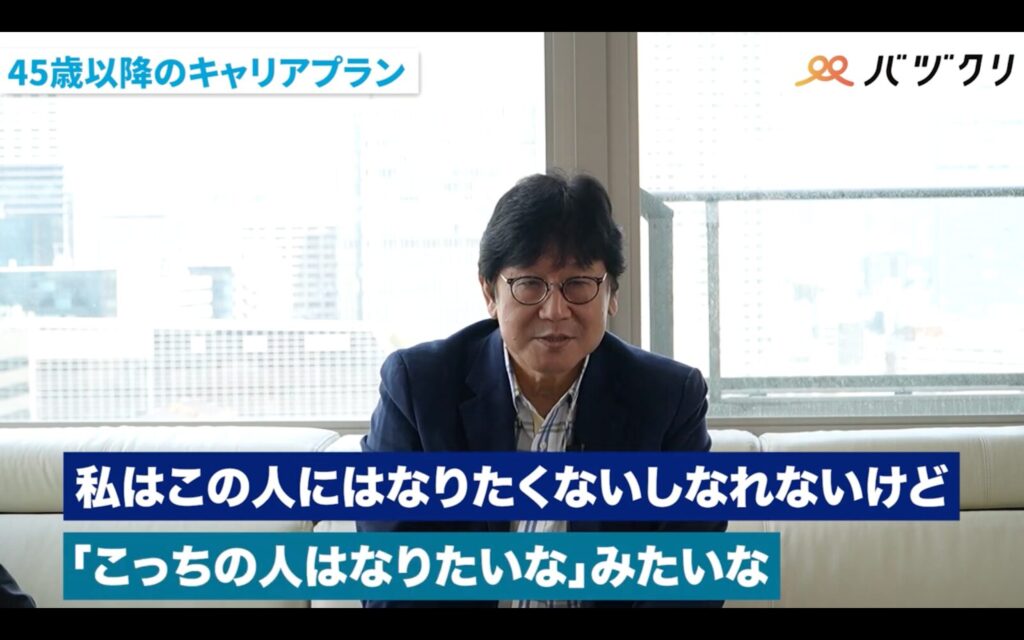
かつては「この人のようになりたい」と思える上司や先輩がロールモデルとなり、キャリア形成の道しるべになっていました。しかし現代は、価値観や働き方の多様化によって、ひとつの理想像に集約しにくい時代になっています。
たとえば「成果を出し続けている優秀なマネージャー」がいたとしても、「自分はあそこまでプライベートを犠牲にして働きたくない」と感じる人もいます。逆に「穏やかな働き方をしながらも信頼を得ている先輩」を理想とする人もいます。つまり、キャリアのロールモデルは単一ではなく、複数のタイプを提示することが必要なのです。
企業が示せるロールモデルのバリエーションが広がれば、社員は「自分に合った目指す姿」を選びやすくなり、キャリア形成に前向きになれます。
補足:プロパー優位説と社内文化の壁
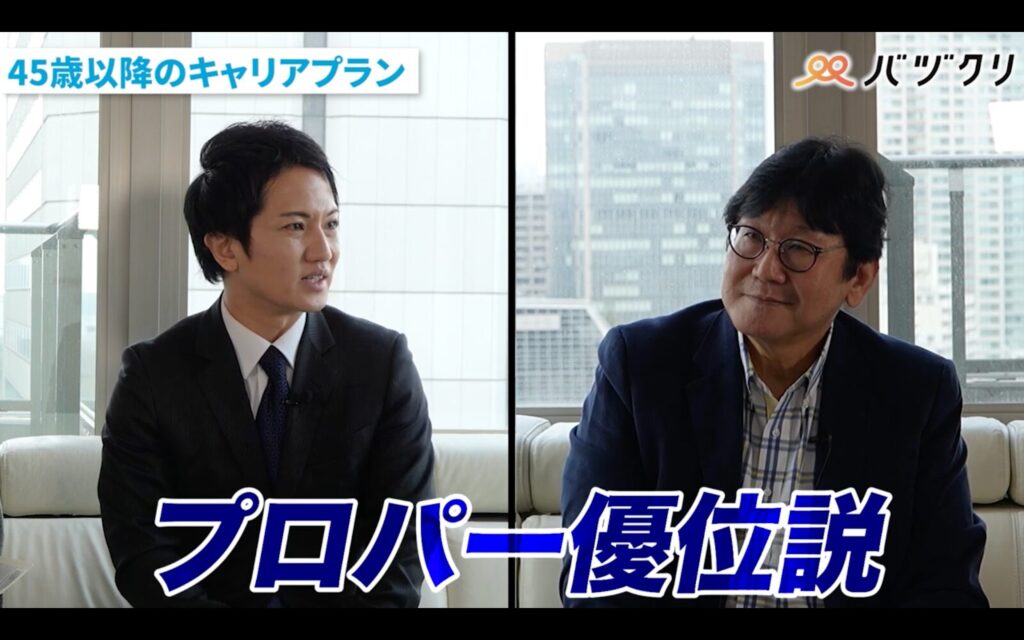
一方で、キャリアを考えるうえで避けて通れないのが組織文化の影響です。
日本企業に根強い「プロパー優位説」つまり新卒から在籍している社員が優遇され、中途社員が活躍しにくいという文化は、今もなお多くの企業に存在しています。
この文化があると、外部から新しい知見を持ち込んだ人材がなじみにくく、ベテラン社員のキャリア形成にも悪影響を及ぼします。既存の序列や慣習にとらわれて「本来活躍できる人材」が埋もれてしまうのです。
したがって、45歳以降のキャリアプランを考える際には、個人の努力だけでなく組織文化の改革も必要であることを忘れてはなりません。
窓際社員予備軍の見抜き方
企業にとって大きな損失となるのは、せっかく採用・登用した人材が早々に「窓際化」してしまうことです。これを防ぐためには、採用や配置の段階で「将来活躍しにくい人材」を見抜く工夫が欠かせません。
ここでは有効な2つの方法をご紹介します。
① コンピテンシーインタビュー
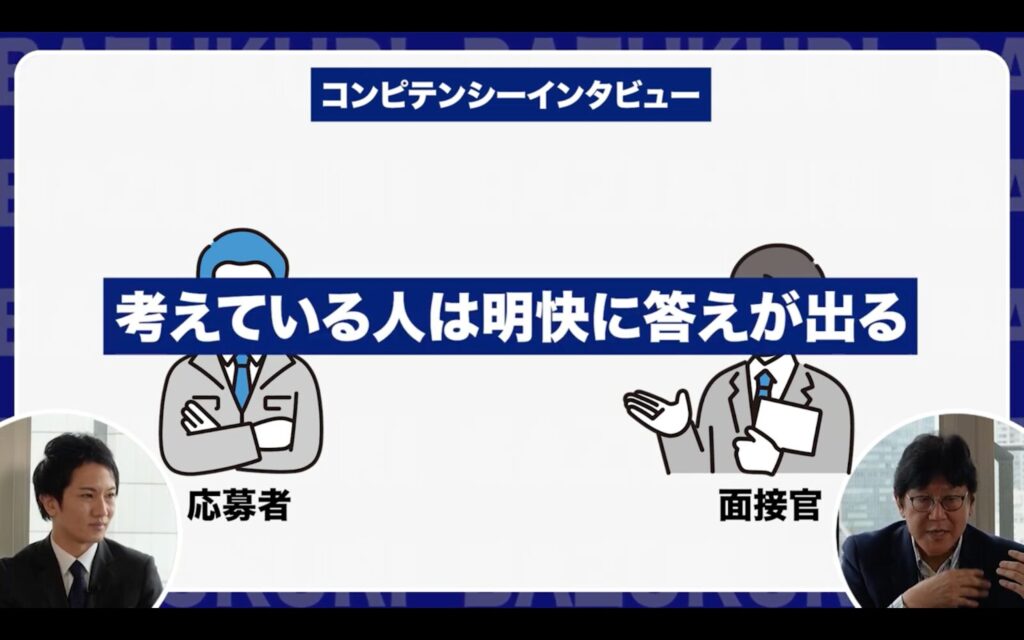
コンピテンシーインタビューとは、応募者や社員に対して「過去の経験を時系列で深掘りし、その行動や考え方を確認する」面接手法です。
例えば「これまでで最も大きな成果を挙げた経験は?」と質問し、
- その成果を達成するために何を考えたか
- どんな行動を取ったか
- 結果どうなり、その後どんな対応をしたか
を順を追って掘り下げていきます。
この方法を用いると、問題解決力や主体性を持つ人は具体的かつ一貫した回答を返してきます。一方で、曖昧な回答や途中で説明が破綻する人は、行動特性として「自ら考えて動けない」傾向が明らかになります。
コンピテンシーインタビューは、将来「自ら学び直し、適応していける人材かどうか」を見極める強力な手段となります。
② アセスメントテスト
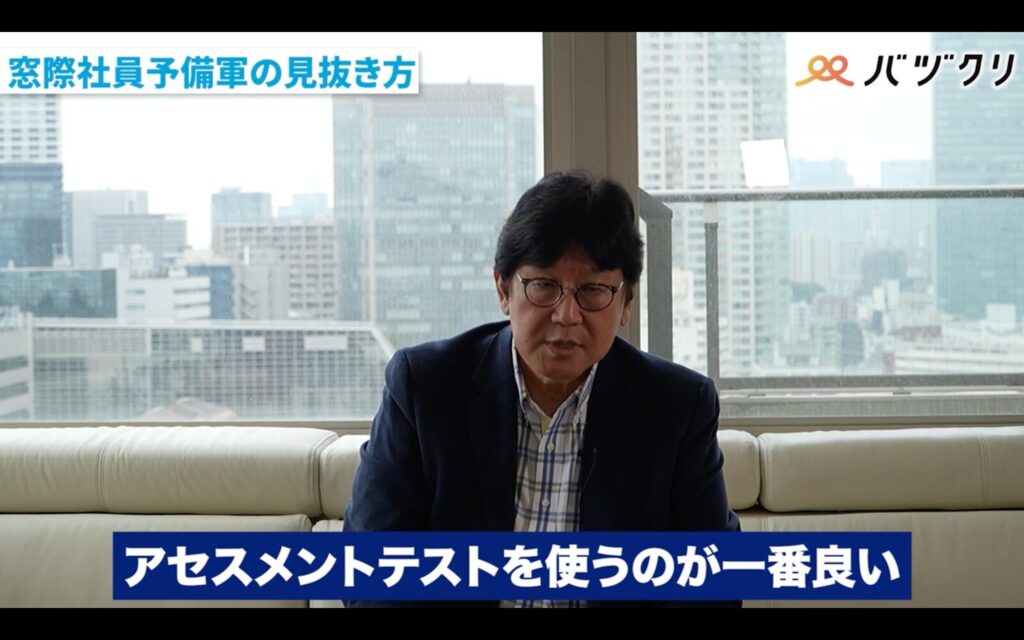
もう一つ有効なのが、動機・価値観・性格など変わりにくい特性を測定するアセスメントテストです。
このテストでは、「この人はどんな行動を取りやすいか/取りにくいか」を可視化できます。例えば、新規事業を任せたいなら「挑戦やリスクを前向きに捉える傾向」が必要ですが、アセスメントを通じてその適性を事前に把握できるのです。
一見すると導入コストが気になるかもしれません。しかし、採用のミスマッチによる損失や早期退職のリスクを考えれば、投資効果は圧倒的に高いといえます。
実際、アセスメントを活用している企業では「配置の的確さ」が増し、採用後のパフォーマンスや定着率に明らかな改善が見られています。
見抜くことは“守り”であり“攻め”でもある
窓際社員予備軍を見抜くことは、単なるリスク回避ではありません。
「活躍しやすい人材を的確に採用・配置できる」ことは、そのまま組織全体の成長スピードを高めることにつながります。
コンピテンシーインタビューとアセスメントテスト、この2つを活用することで、企業は「窓際化リスク」を大幅に減らし、未来志向の人材戦略を実現に近づけることができるのです。
まとめ
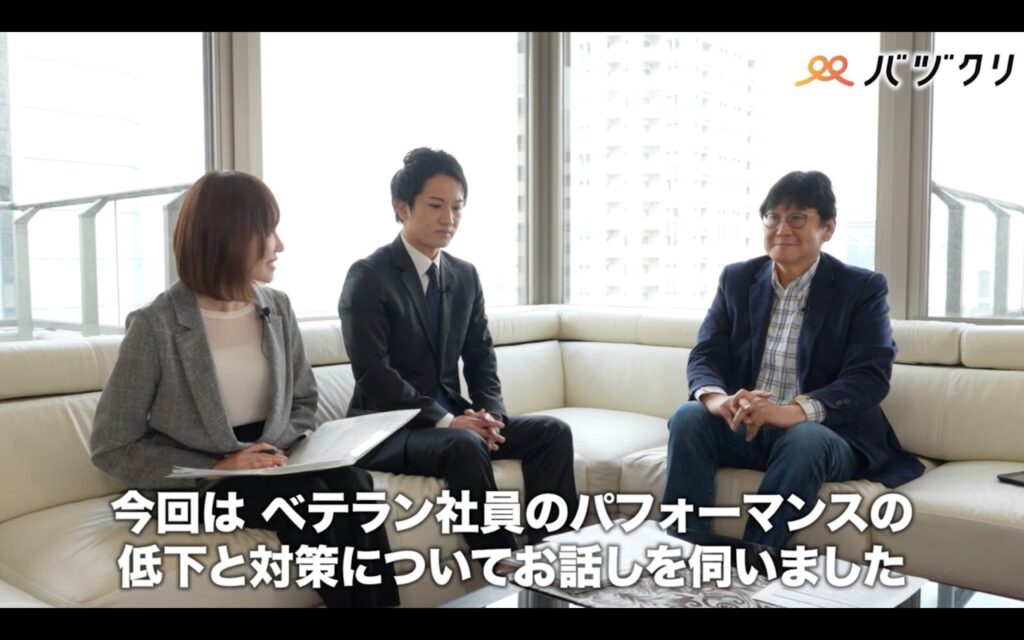
本記事では、専門家対談をもとに「45歳以降のキャリアプラン」と「窓際社員予備軍の見抜き方」について整理しました。
- 会社任せではなく、自分でキャリアを描くマインドセットの転換が必要
- スキルや経験を棚卸しし、強みと不足を明確にすることが出発点
- リスキリングの本質はAIやDXの知識ではなく、土台となるコミュニケーションやマインド
- ロールモデルは一つの理想像ではなく、多様なタイプを提示することが重要
- 採用・配置段階での「窓際化リスク」を防ぐには、コンピテンシーインタビューやアセスメントテストが有効
これらはすべて、ベテラン社員を「窓際」にせず、再び組織の中で輝かせるためのヒントです。
時代の変化は待ってくれません。今こそ、組織のミドル・シニア層のあり方を見直すタイミングかもしれません。
仕事と組織の向き合い方を変える
対話型実践研修「ムキアイ」
「研修はやっている。でも現場は変わっていない気がする」「理論は学んだはずなのに、実践ではうまく使えていない」そんなお悩みはありませんか?
バヅクリの対話型実践研修「ムキアイ」は、身につけてほしい力と、現場で本当に使える力を結びつける、理論と実践の“架け橋”となる対話型実践研修です。
職場に“行動の変化”と“関係性の変化”を起こす研修をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。