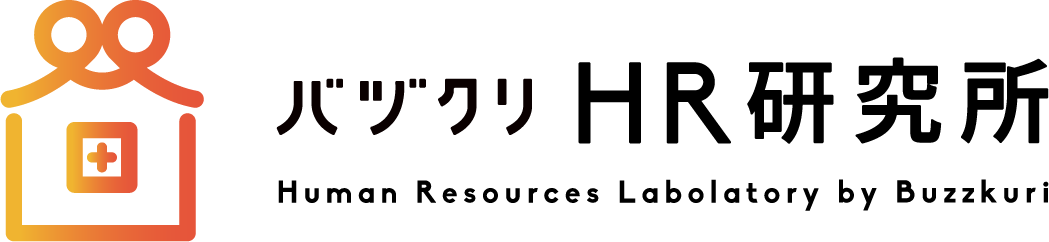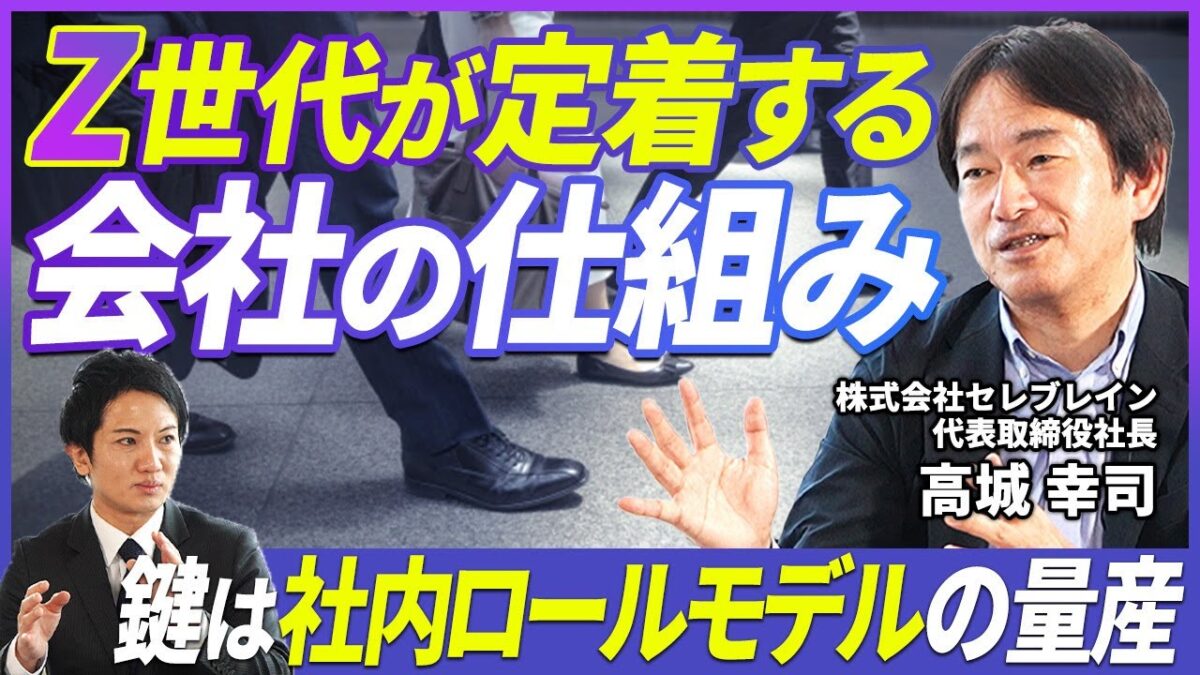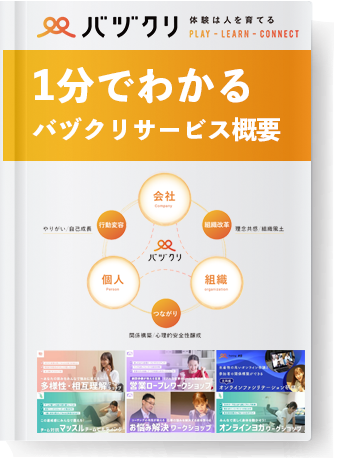本記事は後編です。前編では「若手が辞める本当の理由」をテーマに、成長実感の欠如と人間関係の希薄化という二つの要因を掘り下げました。
▼前編はこちら
後編のテーマは、辞めない組織をどう作るか。
株式会社セレブレイン代表取締役社長の高城幸司さん、そしてバヅクリ株式会社CEOの佐藤太一さんが語るのは、制度や仕組みを超えた「会社の内側をどう温め直すか」という話でした。
インナーブランディング、チーム型マネジメント、ロールモデルの再定義。
ひとつひとつの実践の先に、「もう少しここで頑張ろう」と思える職場のかたちが見えてきます。
目次
登壇者紹介
高城幸司氏(株式会社セレブレイン代表取締役社長)
同志社大学文学部を卒業後、株式会社リクルートに入社。1996年には日本初の独立・起業情報誌『アントレ』を創刊し、事業部長兼編集長を務めました。2001年には著書『営業マンは心理学者』がベストセラーに。2005年より株式会社セレブレインの社長として、人事・人材育成・営業力強化のコンサルティングに従事しています。経営者や管理職への指導経験が豊富で、講演やメディア出演を通じて「人と組織の成長」をテーマに発信を続けています。
佐藤太一氏(バヅクリ株式会社代表取締役社長CEO)
組織開発と人材育成の専門家として、多くの企業のマネジメント改革・次世代リーダー育成を支援。心理的安全性やエンゲージメントを軸にした研修設計に定評があります。経営と人材の橋渡し役として、現場に根ざした制度設計・コミュニケーション改善を提案し、実践的な組織変革を推進。番組では、人材育成の最前線から見た「若手離職のリアル」を冷静かつ温かい視点で語ります。
「伝えているつもり」が一番伝わらない
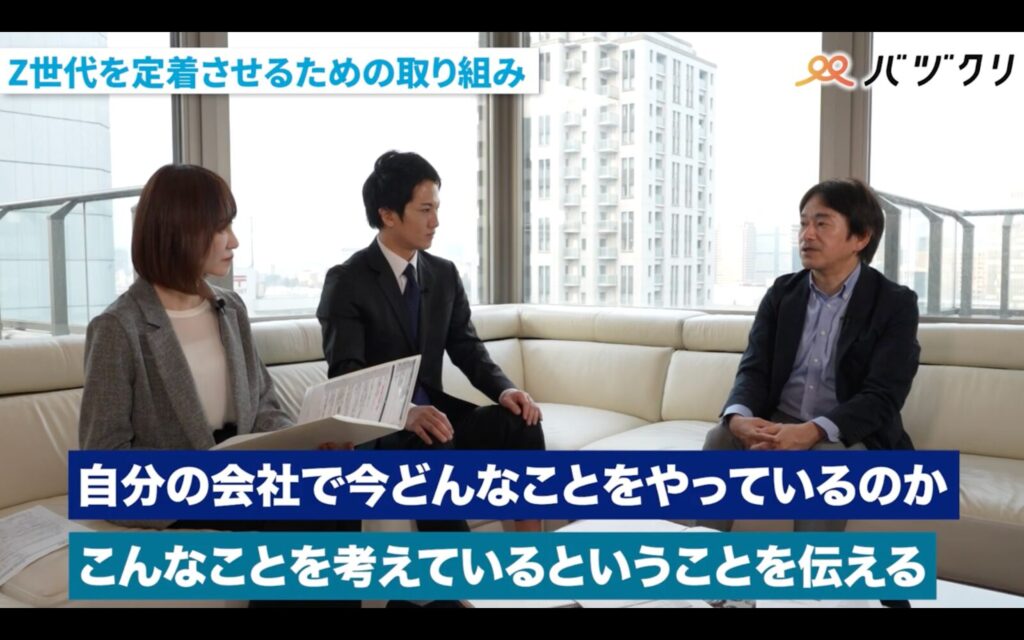
インナーブランディングの再設計
高城さんが最初に指摘したのは、「外には話せているけど、内には届いていない」という構造でした。
「例えば製造業などでもCMを出して採用を目的とした外向きの説明は増えましたが、それと同時に社内にも同じようなことをやった方がいい。
社内には思いが届いていないことが多いんです。だからこそインナーキャンペーンが必要です。」(高城氏)
たとえば新しい経営方針や事業戦略。外部向けの発信よりも、まず社員がそれを自分の言葉で語れるかが鍵になります。
そのために佐藤さんが提案するのが、社内マーケティングの発想です。
「会社の魅力を社員自身にマーケティングする。
うちの会社はこれが強みで、その強みを活かしてこう言う世界を作って、こういうことを目標にしていこうぜっていうのを現場の社員から役員層まで日常会話に出てくるレベルまで刷り込むんです。」(佐藤氏)
「うちの会社は、こういうところがいい」
そう言える社員が増えるほど、エンゲージメントは自然と高まっていく。
伝える努力のベクトルを、外よりまず内に向ける。これが最初の一歩です。
「何かあったら言ってこい」では、誰も言ってこない
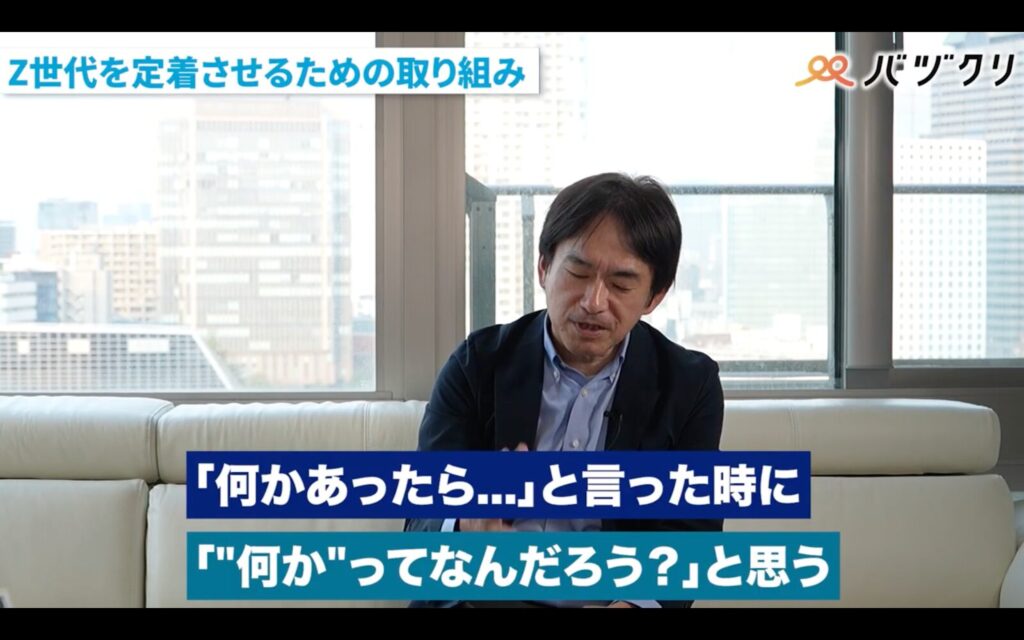
シグナルを察して先に動く上司へ
対談の中で何度も出てきたのが、上司の一言に関する話題です。
「『何かあったら言ってこい』って言う上司、よくいますよね。でも若手にとって”何か”って何?って話なんです。」(高城さん)
この言葉の裏には、受け身のコミュニケーションが潜んでいます。
今の若手はSOSを出す前に次の選択肢を探してしまう。
だからこそ、「シグナルを察知して先に声をかける」動きが求められます。
高城さんは「小さな変化に気づく力」が上司の必須スキルだと言います。
「何かなくても話しかけていく、掘り下げていくといった丁寧なコミュニケーションが重要。ただ大前提、全員がコミュニケーションが上手なわけではないので、会社として仕組みを作ったり、研修をするとか、そういった工夫を重ねていくことが大事です。」(高城氏)
話しかけてくれる上司がいる。それだけで辞める理由はひとつ減ります。
かっこいい社員をつくる
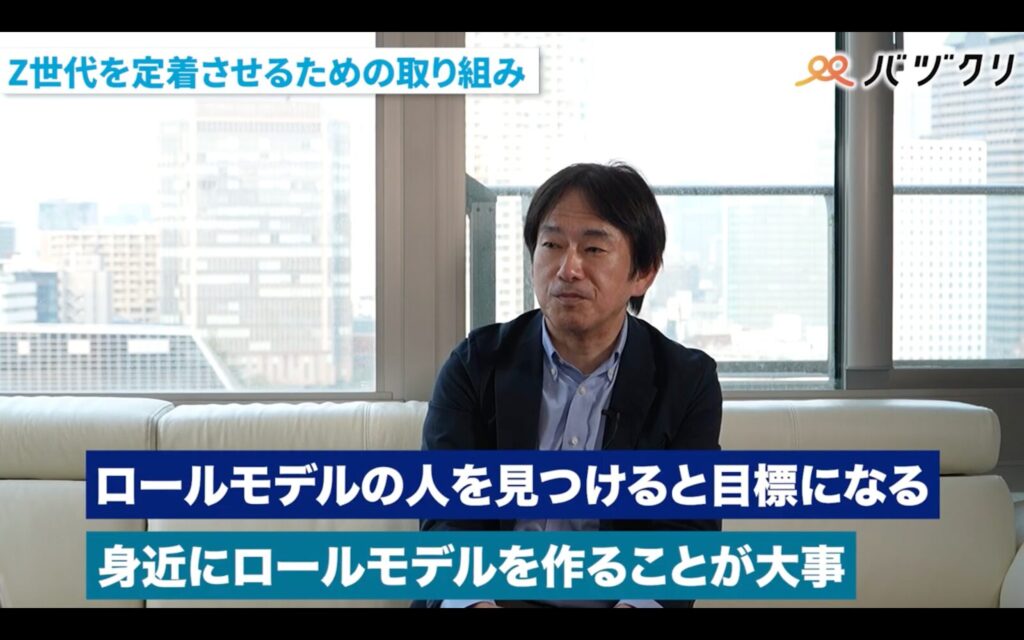
ロールモデルをブランド化するという発想
「ロールモデルがいない」という言葉は、いま多くの職場で聞かれます。
しかし、いないのではなく見せていないだけかもしれません。
「会社の中でこの人みたいになりたいと思える社員を、意図的に作ることが大事です。」(佐藤さん)
たとえば営業職なら、成果だけでなく「どう考え、どう動いたか」を物語にする。
開発職なら、失敗や葛藤も含めたチャレンジの記録を残す。
それを動画や記事で共有し、全社の目に触れる形にする。
いわば、社内インフルエンサーを育てるという発想です。
高城さんもこの点に強く共感します。
「1〜3年目のうちから『こうなりたい』と思える先輩がいると、仕事への向き合い方が変わります。身近にそういったロールモデルをつくっていくことは大事だと思います。」(高城氏)
「憧れ」は人を動かすエネルギー。
そしてかっこいい社員が増えるほど、職場には前向きな連鎖が生まれます。
赤ペン先生は最強のマネジメントツール
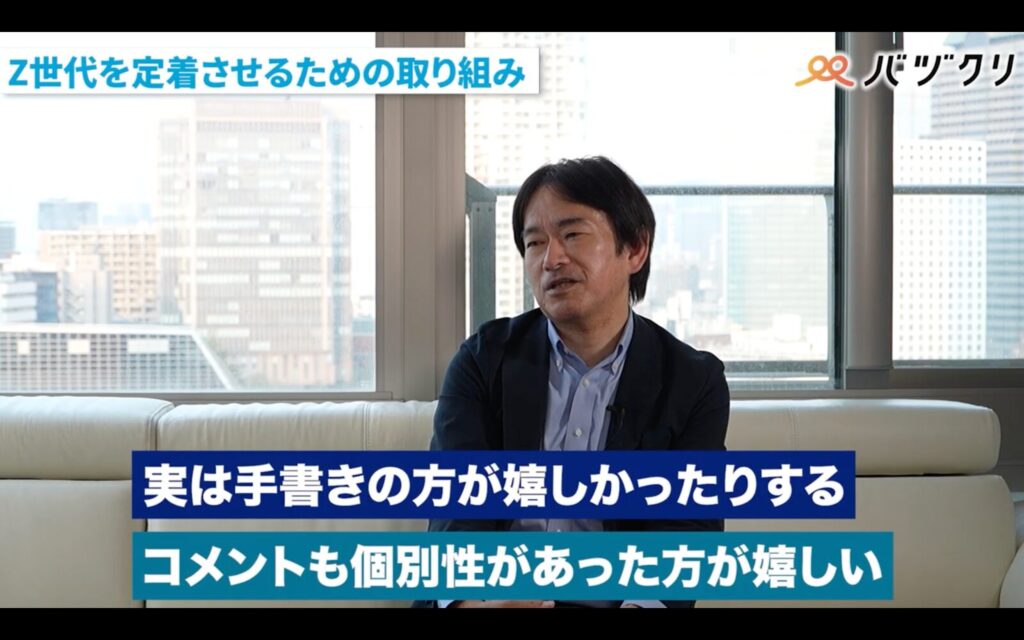
ミドル層を変える観察力と一言の力
離職率の高い現場を立て直したい。そんな相談の多くは、実は「中間管理職の行動変容」が鍵を握ります。
高城さんが紹介した印象的な事例がありました。
「ある会社では日報にハンコを押すだけの習慣をやめて、『よく頑張ってるね』『ここが良かったよ』と手書きコメントを添えるようにしたんです。特に良い部分には赤い付箋を貼る。これを続けたら、離職率が劇的に下がりました。」(高城氏)
赤ペン先生のように見てくれている実感を与えるだけで、人のモチベーションは変わる。
特別な制度よりも、一行の言葉のほうが効くこともある。
「褒める」「気づく」「声をかける」その3つを習慣化することが、最も地道で、最も効果的な離職防止策です。
厳しさと優しさのバランスをどう設計するか
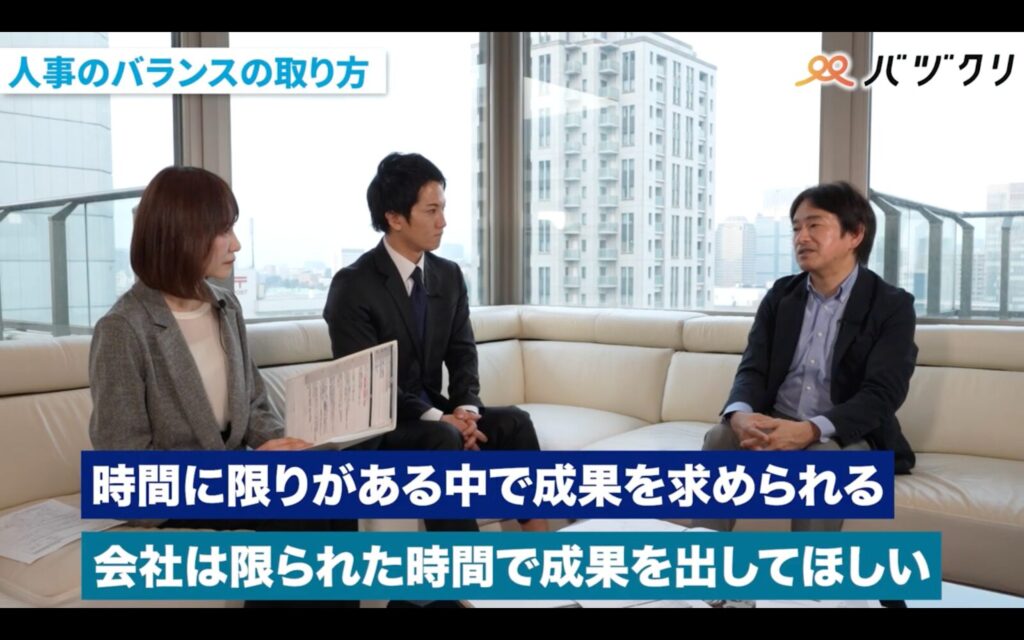
勤務時間内学習の線引きと、伴走のしかた
採用競争が激しい今、働きやすさを前面に出す企業は増えています。
一方で、求職者の一部は「もっと挑戦したい」「厳しい環境で鍛えたい」と考えています。
そんな中、組織としての、そのバランスの難しさについて語りました。
「研修や学びの機会は勤務時間です。人によって習熟度が違うので、ゆっくり学ぶ人に時間外でやってくれとは言いづらい。
長時間残業は許されない時代。どこまでを勤務時間の学びとみなすか、切り分けが必要」(高城さん)
ポイントは、「勤務時間内で学ぶこと」と「自分の意思で学ぶこと」を切り分けること。
会社が責任を持って提供する研修は、時間内でしっかり実施する。
その上で、自己研鑽や興味の拡張は個人の自由に委ねる。
この線引きが曖昧になると、どちらも中途半端になりやすいのです。
高城さんは、こう補足しました。
「上司は、いつまでに何をするかを本人が自分の意思でコミットしているかを確認する。途中の状況を細かく聞き、厳しそうならサポートを入れる」(高城氏)
いきなり自律型を求めるのは現実的ではありません。
最初は密に伴走し、できるだけ早く「自分でペースを作れる状態」へ移す。
付き添いの濃度を段階的に下げる設計が、離職リスクを抑えます。
「今どきの若者は」からの卒業
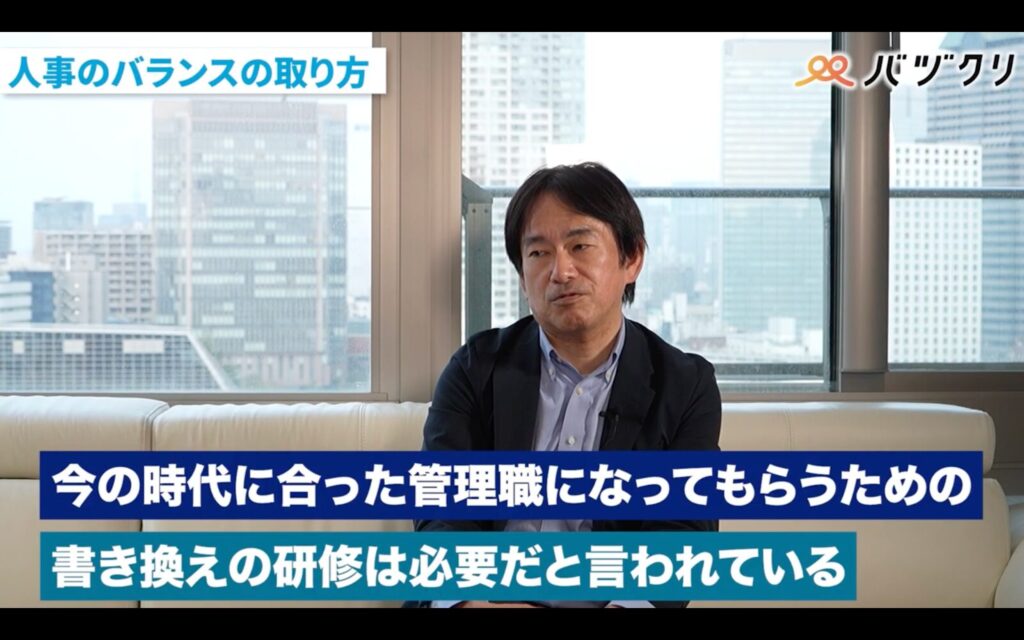
管理職の免許書き換えが必要だ
最後の話題は、世代ギャップの象徴でもある「今どきの若者は」という言葉でした。
高城さんはきっぱりと言います。
「もしその言葉を口にする上司がいたら、その人はもうロールモデルではないということです。」(高城氏)
とはいえ、切り捨てではなくアップデートが必要です。
過去の成功体験のまま止まっている管理職には、免許書き換え型の研修を実施する。
価値観の変化、対話の技法、評価の伝え方。
時代に合わせて上司も学び直す必要があります。
「書き換え研修を受けても変わらない人もいます。でも、変わろうとする意志がある人にはチャンスをあげてほしい。時代が変わっても、育てる仕事の本質は変わりません。」(高城さん)
「制度がある」だけでは人は辞める
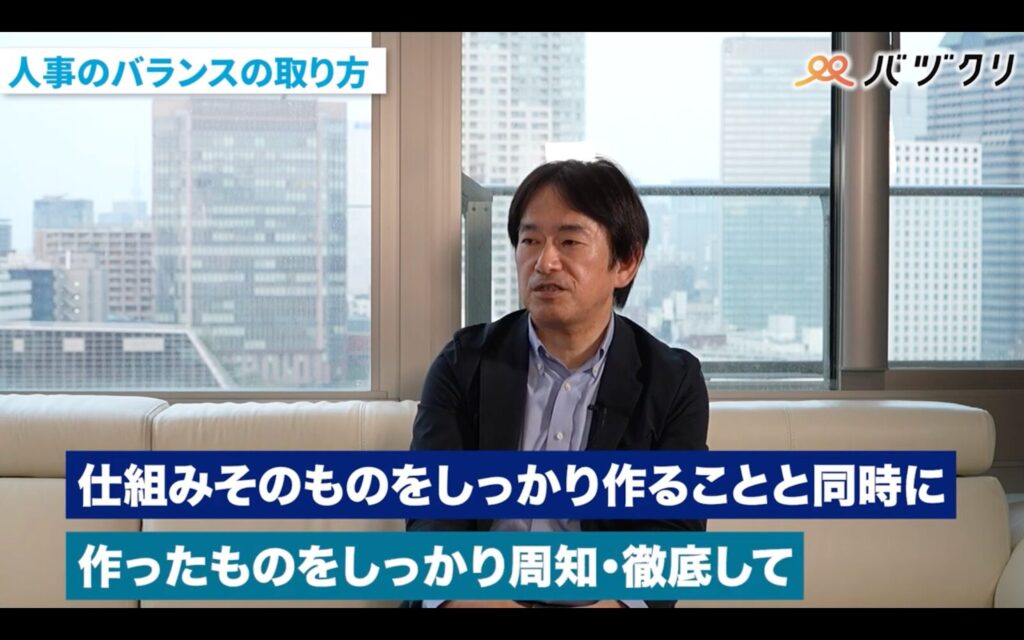
期待役割をわかる言葉で伝える
最後に取り上げたのは、人事制度そのものの伝わらなさです。
「管理職になると何が変わるのか、次にどんな役割を担うのか。制度はあるけれど、新入社員のうちは知らない。そうすると自分がどうなっていくかわからないので頑張りすぎないというケースに陥っていく。」(高城さん)
制度は存在ではなく、作ると同時に社内に周知をして初めて機能します。
そのためには、説明会ではなくワークショップ型の理解促進が有効です。
参加者同士で制度を自分の言葉に置き換え、事例を共有する。
「こうなりたい」という未来像が具体的に描けるほど、制度は血の通った仕組みになります。
離職を減らすことより「もう少し頑張ろう」を増やすこと
後編を通して見えてきたのは、離職を防ぐ方法ではなく、もう少し頑張ろうと思える瞬間をどう作るか、という視点でした。
それは制度でもテクニックでもなく、日常の積み重ねです。
- 社内のメッセージを明確にし、繰り返し伝えること。
- 小さな変化に気づき、声をかけること。
- 憧れられる人をつくること。
- 成長を、対話で支えること。
どれも一朝一夕ではできませんが、確実に組織の空気を変えます。
若手が辞めない組織とは、対話が回っている組織なのかもしれません。
管理職のコミュニケーションスキルをアップデートする対話型実践研修「ムキアイ」
今回の対談で出てきたような「対話」「ロールモデル」「制度の浸透」は、どの企業にも共通するテーマです。
ムキアイは管理職層のコミュニケーションスキルのアップデートを支援する研修を提供しています。
まとめ
「若手を定着させる」と聞くと、多くの人は制度改革や福利厚生を思い浮かべます。
けれど本当に大切なのは、日々の会話の質と会社の温度です。
若手の心が離れるのは、自分が成長している実感がないから。
上司の一言、先輩の姿、制度の一文。
どれもが、彼らにとっての未来へのシグナルです。
あなたの職場では、どんな言葉が日常会話に流れていますか?
少し耳を澄ませてみてください。そこに次の改善のヒントがあります。
▼動画本編はこちら