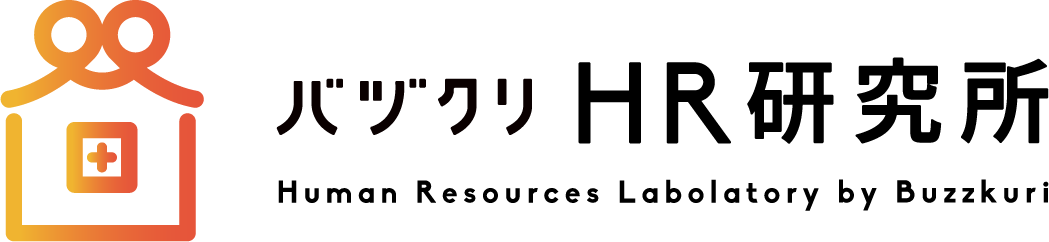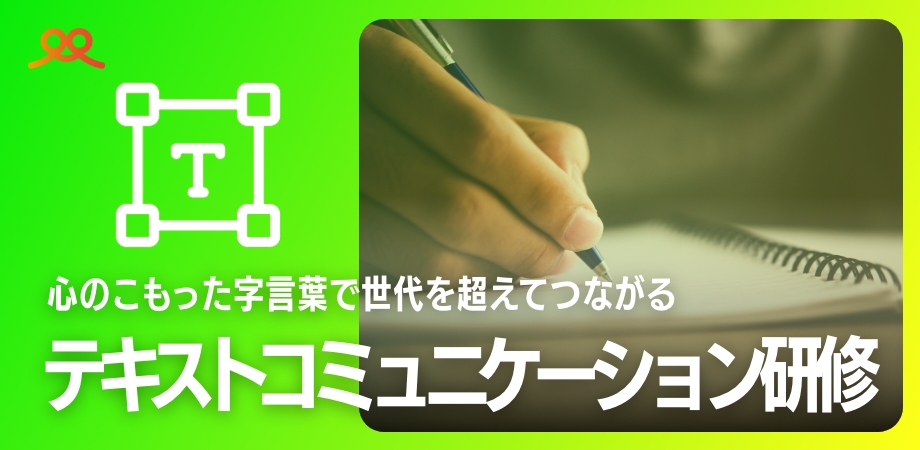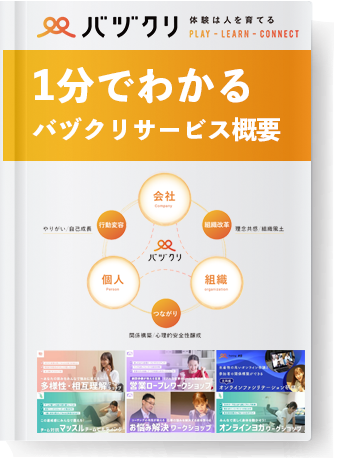テレワークや多様な働き方が進む中で、メールやチャットといったテキストコミュニケーションはビジネスの主流となりつつあります。
文字によるコミュニケーションはナレッジ蓄積やトラブル回避に便利な一方で、表情や声色が伝わらないため、思わぬ誤解やすれ違いを引き起こすこともあります。
本記事では、テキストコミュニケーションの定義やメリット、押さえるべきポイント、注意点を解説します。
目次
テキストコミュニケーションの定義
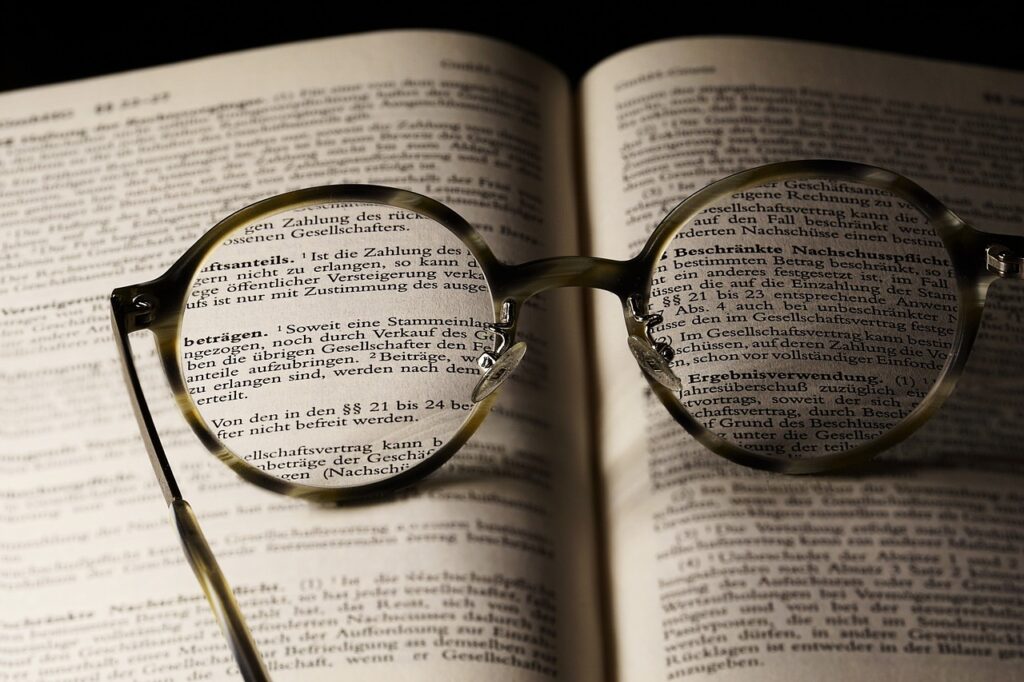
テキストコミュニケーションは、メールやチャットなど文章(テキスト)のみでやり取りするコミュニケーションスタイル。
テキストコミュニケーションには以下の特徴があります。
- 内容が文字で明文化され、情報が可視化されるため、組織のナレッジを蓄積しやすい
- 履歴を検索したり見返したりできるため、「言った/言わない」トラブルを防げる
こうした特徴を持つテキストコミュニケーションは、時差勤務やリモートワーク、海外拠点との連携など、多様な人材と協業する際に重宝します。
一方、表情や声色が伝わらない非対面コミュニケーションであるため、書き手には分かりやすく、親しみやすい文章を書くスキル、読み手には相手の意図を的確に読み取る読解力が求められます。
テキストコミュニケーションが重要視され始めた理由
テキストコミュニケーションが重要視された背景には、テレワークの普及があります。
コロナ禍以降、出社前提の働き方からテレワークへの移行が起こり、メールやチャットで業務に関するコミュニケーションを行う機会が急増しました。
また近年、日本企業は働き方改革に対応するため、育児や介護など多様なライフイベントを抱えながらも働き続けられるテレワーク環境を整えてきました。
一方、言葉以外に表情や声量で情報を伝えるオフラインコミュニケーションと、簡潔に分かりやすく物事を伝える必要があるテキストコミュニケーションでは、求められるスキルも異なります。
人材不足が加速する中で、テレワーク下での仕事がスタンダードとなる職場では、円滑にビジネスを進めるためにテキストコミュニケーションを前提にしたスキル開発が重要視されるようになりました。
世代間のコミュニケーションギャップ
また、テキストコミュニケーションの重要性が高まっているもう一つの背景として、職場における世代間のコミュニケーションスタイルの違いがあります。
対面や電話でのコミュニケーションを中心に仕事をしてきたベテラン世代と、デジタルネイティブであるZ世代では、テキストコミュニケーションに対する期待や理解が大きく異なることがあります。
例えば、Z世代は簡潔な短文や絵文字を使った素早いやり取りを好む傾向がある一方、ベテラン世代はより丁寧で詳細な文章構成を重視する傾向があります。
こうした世代間のコミュニケーションギャップは、チームの生産性低下や意思疎通の齟齬を招くリスクがあります。
異なる世代が同じ職場で協働する現代のビジネス環境では、世代を超えて「伝わる」テキストコミュニケーションのルールを共有し、互いの特性を理解することが、チームの一体感を高める鍵となっています。
テキストコミュニケーションのメリット

ビジネスにおけるテキストコミュニケーションは、情報の正確な共有や業務効率化、グローバル対応力の向上など多くのメリットがあります。
ここではテキストコミュニケーションのメリットを紹介します。
情報の正確な記録と共有が容易
テキストコミュニケーションが中心のチームでは、チャットやメールのログにこれまでの発言が蓄積されているため、口頭でのコミュニケーションが中心のチームより「言った/言わない」の行き違いを減らすことができます。
また、コミュニケーションの履歴を追うことができるチームでは、新メンバーが途中から参加しても情報のキャッチアップが容易になります。
時間と場所を選ばない非同期コミュニケーション
非同期コミュニケーションとは、各自が都合の良いタイミングでメッセージを確認したり、返信できたりするコミュニケーション手段のこと。
メールやビジネスチャットといったテキストコミュニケーションも、非同期コミュニケーションの一つです。
非同期コミュニケーションは各自のペースでやり取りができるため、時差がある海外の社員や、フレックスタイム制で働くメンバーなど、リアルタイムで集まることが難しい人とも協業しやすくなります。
また、テキストコミュニケーションは自分でメッセージを見るタイミングを自由に選べるため、集中力を維持しながら業務に取り組むことができます。
思考の整理と論理的表現の訓練になる
テキストに自分の考えを書くことは、「自分は何を伝えたいのか」「何を/どの順番で/どう伝えると伝わりやすいか」を考える訓練になります。
テキストコミュニケーションを日常的に行うチームでは、自分の考えを整理する習慣と、論理的思考力(ロジカルシンキング)が鍛えられるため、普段のミーティングや提案の場面でも、意見の説得力が増しやすくなります。
論理的思考はプレゼンや資料作成などにもつながる、ビジネスパーソンとして必須のスキルと言われており、テキストコミュニケーションによって論理的思考力を養うことは、将来的なキャリアアップにも役立ちます。
言語の壁を越えやすい
テキストコミュニケーションは、翻訳ツールとの相性も非常によいため、海外出身のメンバーがいるチームでもスムーズに意思疎通しやすくなります。
リアルタイムかつ口頭コミュニケーションが前提となる国際プロジェクトでは、参加者に高い言語レベルが求められたり、新たに通訳を雇う必要があったりなど、コミュニケーションコストが余分にかかります。
多国籍チームを組成する場合は、テキストコミュニケーションを中心に業務を設計することで、低コストかつスピーディに業務を進めることができるでしょう。
テキストコミュニケーションのポイント

対面とは異なり、表情や声のトーンが分からないテキストコミュニケーションでは伝え方に工夫が必要です。
本記事では、テキストコミュニケーションならではの伝え方のポイントを解説します。
5W1Hを意識した明確な情報伝達
「5W1H」とは、英語における6つの疑問詞をまとめたもので、誰が(Who)・なぜ(Why)・何を(What)・いつ(When)・どこで(Where)・どうやって(How)を指します。
この5W1Hを意識して文章を作成することで、自分の伝えたい意図が伝わりやすくなり、コミュニケーションが簡潔になりやすくなります。
たとえば「営業メンバー全員で(Who)、今期の営業活動の振り返りのため(Why)、営業会議を(What)、明日10時(When)、会議室で(Where)行います」と伝えれば、「なぜやるのか?」「参加者は誰なのか?」といった追加の質問は起こりにくくなります。
誰が読んでも分かりやすいコミュニケーションを実現するために、5W1Hを意識しましょう。
結論から伝える「PREP法」の活用
PREP法とは、「Point(結論)→ Reason(理由)→ Example(具体例)→ Point(再主張)」の順で伝えるテクニックです。
具体的には、「このツール導入を推奨します(結論)。なぜなら作業時間を半減できるからです(理由)。実際、導入企業では生産性が30%向上しました(具体例)。だからこそ推奨します(再主張)」とPREP法の流れで意見を主張すると、複雑な情報も伝わりやすくなります。
反対に、何が言いたいか結論がなかなか見えない文章は、読み手を混乱させるリスクがあるので注意しましょう。
簡潔にまとめて文を送る
テキストコミュニケーションで書くテキストは、読み手が短時間で理解できるように、簡潔にまとめましょう。
読みやすさを向上させるためには、余分な背景説明は省き、最小限の修飾や箇条書きを活用しながら、要件・目的・必要なアクションを伝えるとよいでしょう。
例えば「次回mtg:○月○日(月)12:00〜@zoom」など、簡潔に記述することで、スマホなどの小さな画面で見ても重要な情報を取りこぼしにくくなります。
絵文字や言い回しなどで、雰囲気づくりを心がける
テキストコミュニケーションのデメリットは、感情が伝わりづらく、読み手に冷たい印象を与えてしまうことです。
たとえば「了解しました」という一言を送る際にも、語尾に絵文字をつけたり、「!」をつけたりすると、柔らかい印象になりやすくなります。
意図せず「無愛想だ」と思われて関係が悪化してしまうリスクを防ぐためにも、温かみを感じる文章を心掛けましょう。
テキストコミュニケーションの注意点

テキストコミュニケーションは便利な一方で、注意点を理解せずに頼りすぎると重大なトラブルを招く恐れがあります。
ここでは、それぞれの注意点と対策方法を紹介します。
曖昧な表現を避ける
テキストコミュニケーションでは、声のトーンや表情など対面では伝えることができていた細かいニュアンスを伝えることができません。
そのため「なるべく早く」や「できれば」など、読み手によって解釈が変わる曖昧な言葉遣いは誤解を生みやすくなります。
そういった誤解を避けるためにも、5W1Hを意識した文章を心がけましょう。
緊急時には不向き
テキストコミュニケーションは、こちらが送信してもすぐに相手が読んでくれるとは限らないため、緊急時やトラブル発生時の連絡には適しません。
どうしてもすぐに対応して欲しいことがある場合は、電話やビデオ通話など、テキストではない同期コミュニケーションをとりましょう。
ツールの特性を理解する
コミュニケーションツールにはそれぞれ特徴があります。
例えばチャットツールは短文かつカジュアルなコミュニケーションに向いており、メールは取引先のやりとりなどオフィシャルなテキストコミュニケーションに向いています。
テキストだけでは伝えにくい複雑な議論をしたい場合は、ビデオ通話ツールを活用した方が良い場面もあるでしょう。
一つのツールにこだわると、コミュニケーションの効率が落ちる可能性があるため、目的やシーンに応じてツールを適切に使い分けることが重要です。
情報セキュリティへの配慮
テキストコミュニケーションでは、情報漏洩リスクに特に注意が必要です。
例えば、誤送信やアカウント乗っ取りによって機密情報が社外に流出してしまうと、企業の信頼性が失われてしまいます。
これらを防ぐためには、ログイン時の2段階認証を導入する、従業員へ向けて定期的に情報セキュリティ研修を実施する、サイバー攻撃のリスクに備えてセキュリティ対策を強化するなど、全社的なセキュリティ意識の向上が必要です。
バヅクリの研修「ムキアイ」のテキストコミュニケーション研修
バヅクリの研修「ムキアイ」のテキストコミュニケーション研修は、黙々と個人で学ぶ形式ではなく、受講者同士で対話しながら進めるワークを取り入れているのが特長です。
本研修では、単なる言葉遣いのテクニックにとどまらず、世代や背景の異なる相手にも「伝わる」字言葉を意識したコミュニケーション力を養成します。
実践型グループワークを通じて、曖昧な表現を避ける技術や、テキストだけで温かみを伝える工夫を学べる内容となっており、若手から中堅社員まで幅広い層のコミュニケーションスキル向上に貢献します。
まとめ
テキストコミュニケーション力は、単に文章をやり取りするだけでなく、相手に意図を正しく伝え、信頼を築くために欠かせないスキルです。
テレワークや多様な働き方が進む今、誤解を減らし、円滑に仕事を進めるためには、意識的なトレーニングが必要です。
今回ご紹介したポイントを参考にしながら、実践的なスキルをさらに磨くために、テキストコミュニケーション研修の実施を検討されてみてはいかがでしょうか。