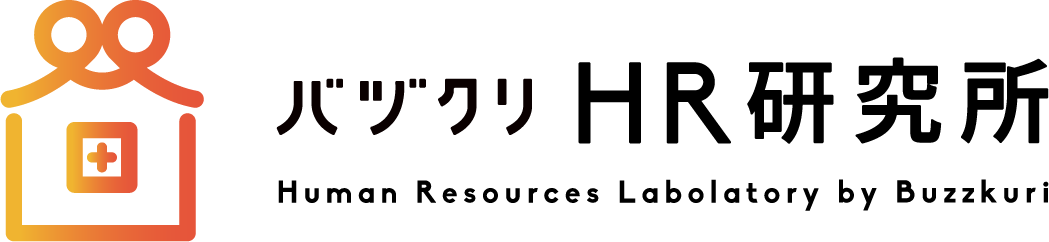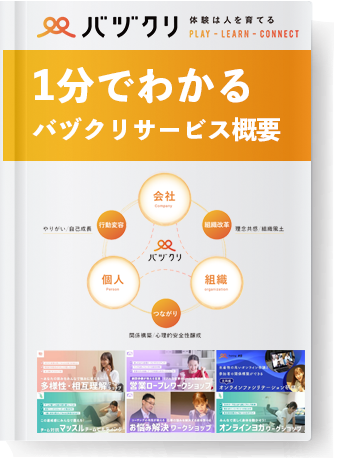人事の現場で「なぜあの人を採用してしまったのか…」という後悔の声は後を絶ちません。今回の対談では、株式会社キープレイヤーズ代表であり、70社以上にエンジェル投資を行い、4,000人以上の経営者を支援してきたキャリアコンサルタント・高野秀敏氏と、組織開発と人材育成のプロであるバヅクリ株式会社代表の佐藤太一氏と組織を崩壊させる危険な人材の特徴について語ります。
本記事では、『キープレイヤーズ高野氏と組織開発プロが語る「早く出世する人の5つの共通点」』に続く第二弾として、経営者や人事が避けるべき“ネガティブな人材”の具体像と採用段階での見抜き方を紹介します。
▼動画本編はこちら
目次
対談で挙げられた「組織をダメにする人材」の6タイプ
本対談では、組織の健全性を損なう可能性のある6つの人材タイプが紹介されました。
一見すると能力もありそうな人材であっても、こうした資質を持っている場合、周囲に悪影響を与えたり、文化を乱したりするリスクがあります。
では、それぞれのタイプについて詳しく見ていきましょう。
1. ネガティブな発言を無意識に発する人
職場の雰囲気は、たった一言の「愚痴」から崩れ始めることもあります。
ネガティブな人材は、無意識のうちに不満や悪口を発してしまい、その空気がチームにじわじわと広がっていきます。
しかも本人はそれが“普通の会話”だと思っており、悪気がない分、発見や修正が困難です。
特徴と影響
- 仲間や会社に対する不満・批判を、無意識のうちに発する
- 飲み会や雑談の中で愚痴を垂れ流す
- 周囲に悪影響を与える“伝染性”がある
採用時の注意点
面接ではネガティブな一面は出さないため、リファレンスチェックや、具体的なエピソードベースの質問で見抜く工夫が必要です。
2. 組織に“邪気”を持ち込む人
一見ポジティブでエネルギッシュに見えても、実は「自己利益」だけを追求する人もいます。
「御社のビジョンに共感しました」という姿勢で入社しながら、実際には「どうすれば自分が得できるか」ばかりを考えている。
このような人材は、チームワークを軽視し、全体最適よりも個人最適を優先する傾向があります。
特徴と影響
- 表向きはミッション・ビジョンに共感するが、内心は“自分の利益”優先
- 「どう楽するか」「早く帰るか」ばかり考えている
- 利己的なスタンスがチームの士気を下げる
採用時の注意点
志望動機が耳障りの良い言葉に終始していないか注意を。行動レベルの価値観を深掘る質問が効果的です。
3. 責任転嫁をする“無責任”な人
「結果が出なかったのは自分のせいではない」と考える癖がある人は、学習も成長もしません。
このタイプの人は、何かうまくいかなかった時に、環境や他者、時には制度のせいにしがちです。
一見すると合理的なようで、実は「改善しよう」という視点が抜け落ちているのが特徴です。
特徴と影響
- 失敗の原因を環境や他人のせいにする
- 「マーケットが悪かった」「タイミングが合わなかった」などの言い訳が多い
- 自責意識がなく、成長が止まる
採用時の注意点
「過去の失敗体験」を聞くことで、自責か他責かのスタンスを測定。自分の改善点に言及するかがカギです。
4. 自分で決められない人
意思決定の場面で「自分で決めることができない」人は、現場においても主導権を持てません。
常に誰かの指示や周囲の空気に従ってしまうため、自律的な行動が求められる環境では力を発揮しにくくなります。
特にベンチャーやスタートアップのような、曖昧な状況下での判断が多い現場では、この特性が大きな足かせとなる可能性があります。
特徴と影響
- 「上司がこう言ったから」「家族に言われたから」といった他責的な言動
- モチベーションが他人の判断に左右される
- 判断力や主体性に欠ける
採用時の注意点
「自分の意思で選択・決断した経験」があるかを問う質問が有効です。環境ではなく“自分起点”の語り方かどうかを見ましょう。
5. ルールを破る人
「自分だけは特別」「多少の逸脱は許される」という認識がある人は、組織の信頼や一体感を崩壊させかねません。
ルールを守らない行動が続くと、他のメンバーにも悪影響が及び、やがて組織全体の規律が崩れていきます。特に権限がある立場であればあるほど、そのインパクトは大きくなります。
特徴と影響
- 就業規則やルールを軽視する
- チーム内で特例扱いされることを当然と考える
- 周囲のモラル低下や不満の連鎖を招く
採用時の注意点
過去の職場での行動や倫理的判断に関するエピソードを深掘りし、組織ルールへの認識や遵守姿勢を確認しましょう。
6. 教科書通りにしか動けない人
「決まったことはできるが、想定外には弱い」——このタイプは変化を続ける組織にフィットしづらい傾向があります。
マニュアルやルールを正確に守ること自体は悪いことではありませんが、それだけでは柔軟な問題解決はできません。
新しいチャレンジや未知の課題に向き合う際、自ら考え、行動できるかどうかが問われます。
特徴と影響
- 「マニュアルに書いてあるから」と指示待ち思考
- 自ら仮説を立てて動けない
- 想定外の事態に弱く、組織の変革を阻む
採用時の注意点
「マニュアルのない状況での判断経験」を聞き出すことで、思考の柔軟性や創造性を評価できます。
まとめ:スキルより“価値観”を見る採用へ
いまや「何ができるか」よりも「どんな姿勢で仕事をするか」が重要視される時代。スキル重視の採用から、“組織を壊さない人”を見極めるバランス型の採用が求められています。
ベンチャーや変化の多い組織においては、たった一人の人材が大きな波紋を広げることもあります。「組織に合う人材」という観点での判断力が、経営者・人事担当者の真価を問われる場面と言えるでしょう。
▼動画本編はこちら
仕事と組織の向き合い方を変える
対話型実践研修「ムキアイ」
「研修はやっている。でも現場は変わっていない気がする」「理論は学んだはずなのに、実践ではうまく使えていない」そんなお悩みはありませんか?
バヅクリの対話型実践研修「ムキアイ」は、身につけてほしい力と、現場で本当に使える力を結びつける、理論と実践の“架け橋”となる対話型実践研修です。
職場に“行動の変化”と“関係性の変化”を起こす研修をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。