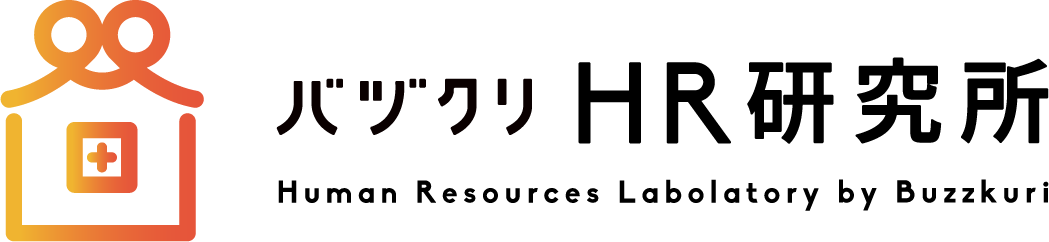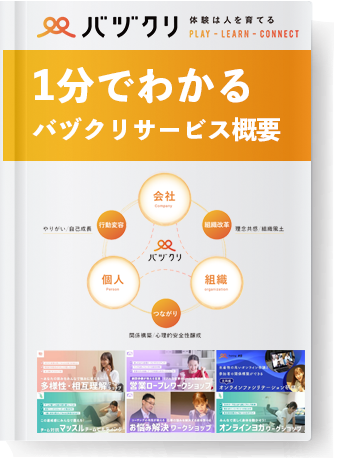生成AIの急速な普及により、AIスキルは一部のエンジニアだけでなく、全社員が身につけるべき基本スキルとなりました。
しかし「何を」「どこまで」「どのように」学ばせるべきか、明確な基準がないまま研修を実施し、投資対効果を得られない企業も少なくないのが実情です。
本記事では、一般社員に本当に必要なAIスキルを明確化し、目的・形式・料金の観点から厳選した9つの研修サービスを徹底比較。
戦略的な人材育成を実現するための具体的な選び方とポイントを解説します。
仕事と組織の向き合い方を変える
対話型実践研修「ムキアイ」
「研修はやっている。でも現場は変わっていない気がする」「理論は学んだはずなのに、実践ではうまく使えていない」そんなお悩みはありませんか?
バヅクリの対話型実践研修「ムキアイ」は、身につけてほしい力と、現場で本当に使える力を結びつける、理論と実践の“架け橋”となる対話型実践研修です。
職場に“行動の変化”と“関係性の変化”を起こす研修をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
目次
AI研修が企業の未来を左右する?
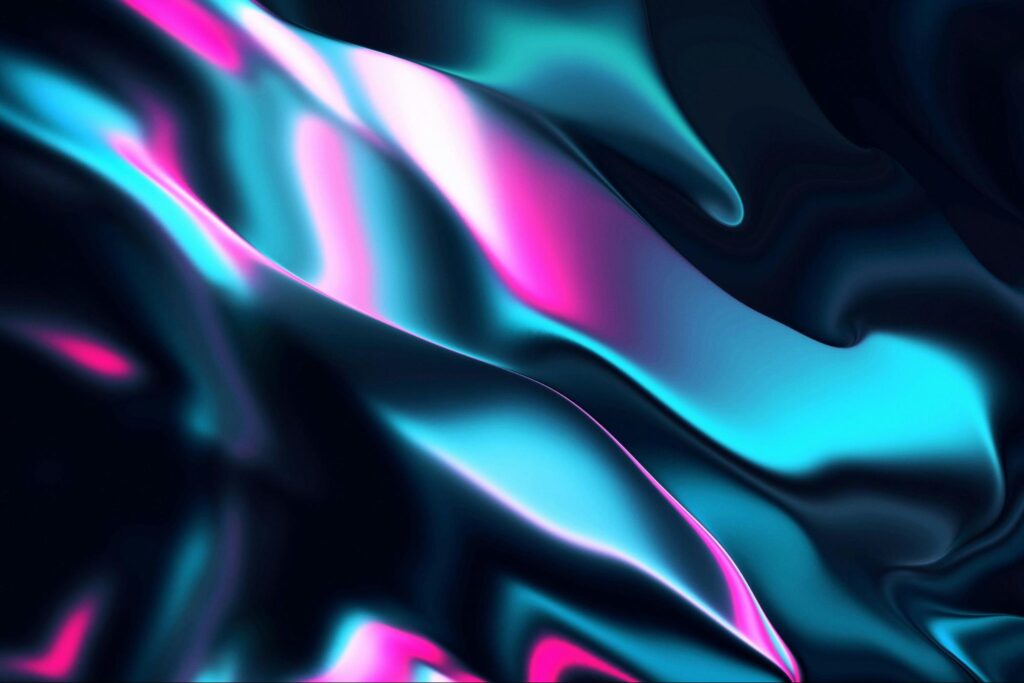
AIがビジネスシーンに本格的に浸透しつつある今、なぜ企業がAI研修に取り組むべきなのか解説します。
全社員の「+10%」が生産性を劇的に向上させる
アメリカのビジネス誌「Fortune」の調査によると、「AIアシスタントを活用した労働者は13.8%生産性が高い」という結果が報告されています。
一見すると、「13.8%」という数値はインパクトが少ないように感じますが、もしこの生産性向上が全社に普及すれば、その影響は大きなものになります。
そこで重要なのが、一部の先進的な社員だけがAIを使いこなせる状態を脱却し、全従業員が日常的な業務でAIを活用できるようになること。
AIによる全社的な業務効率化を達成することが、創造的な業務をする余白を生み出し、イノベーション創出を加速させます。
社員間で生まれる「社内デジタルデバイド」のリスク
AI活用スキルの社員間格差は、新たな「社内デジタルデバイド」を生み出し、組織の分裂を招きます。
すでに、AIを使いこなす社員とそうでない社員の間で、業務スピードや提案の質に明確な差が生まれている企業も多いです。
このギャップを放置すると、チーム内での不公平感や、AIスキルのない社員の自信喪失につながり、組織全体のモラール低下を招きます。
全社一律でAI研修を行うことは、こうしたリスクを未然に防ぎ、組織の結束と競争力向上につながる重要な投資なのです。
全社員向けAI研修で何を学ぶ?押さえるべき2つの必須テーマ
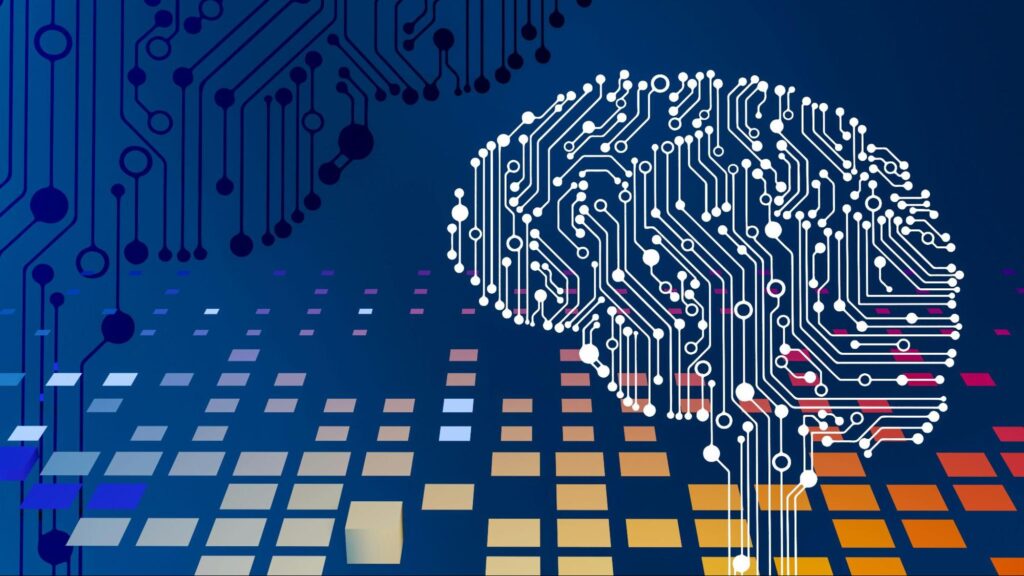
AI活用を推進するために、すべての社員が研修で学ぶべき2大テーマとはどんなものでしょうか。
1.全員必須の「守りの知識」:AIリテラシー
生成AIツールが急速に普及する中で、機密情報の漏洩や著作権侵害、AI生成コンテンツの誤用によるブランドイメージの損失が様々な企業で起こっています。
全社員がAIの基本的な仕組みと限界を理解していないと、気づかないままリスクを犯してしまい、最悪の場合企業の信頼性失墜にもつながる危険性もあります。
AIの基本的な仕組みやリスクの理解・社内ルールの浸透など、これらのAIリテラシーは企業リスクを回避するために全社員が学ぶべき、いわば「守りの知識」です。
2. 日常業務を変える「攻めのスキル」:業務効率化
AIリテラシーを学習した上で、実際にAIを活用してどのように業務効率化を行うか、実践につながる知見もAI研修で学ぶべきテーマです。
定型的な文書作成やメール対応、データ整理といった日常業務の自動化スキルに加えて、市場調査や競合分析、アイデア発想でもAIは大いに活用できます。
部門の業務に応じた活用事例を学ぶことで、従業員一人ひとりが「自分の仕事にAIをどう活かすか」を具体的にイメージできるようになります。
全社員向けAI研修で失敗しないための選び方3つのポイント

ここでは外部のAI研修プログラムを探す際に、失敗しないためのポイントを紹介します。
ポイント1:研修の「目的」と「レベル」は自社に合っているか
まずは自社の現状と目指すゴールを明確化しましょう。
「AIの基礎的な知識をつけたい」のか「実践的に活用してほしい」のかで、選ぶべき研修は大きく異なります。
前者なら概念理解中心のeラーニング形式、後者なら手を動かすワークショップ形式が適しています。
また、従業員のITリテラシーレベルも重要な判断基準です。
一定のレベルの社員が多い企業ならより高度なノウハウを、基本的なPC操作に不安がある社員が多い場合は段階的なアプローチが必要です。
ポイント2:「明日から使える」実践的な内容になっているか
「研修を受けたその日から実際の業務でAIを活用できるか」という視点も重要です。
単なる座学ではなく、実際にChatGPTやMicrosoft Copilotなどの業務で使用するツールを操作して、実際の業務に近い内容の演習(ハンズオン学習)ができることが望ましいでしょう。
自社のセキュリティポリシーと照らし合わせながら、使用可能なAIツールを事前に確認し、それらを実際に操作できる研修プログラムを選びましょう。
ポイント3:研修形式は、受講規模や環境に合っているか
全社展開を前提とした研修では、実施形式の選択が成功を大きく左右します。
数百人規模での展開を考えているなら、時間と場所の制約が少ないeラーニング形式が現実的です。
一方で、部門単位での深い学習を重視するなら、講師との双方向コミュニケーションが可能な集合研修やオンライン研修が効果的です。
リモートワークが中心の企業ならオンライン完結型の研修、現場作業が多い職種を含む場合は短時間で完結するマイクロラーニング形式など、従業員の環境に合わせて最適な形式を洗濯しましょう。
全社員向けAI研修サービス 比較一覧

【比較表】おすすめ研修会社 一覧早見表
| 会社名 | AI研修の特徴 | 研修形式 | 料金目安 |
| バヅクリ株式会社「ムキアイ」 | 業務への活用や効率化のアイデアを得ることをゴールに、ワークを重ねることで使い方を理解 | 対面/オンライン | 要問い合わせ |
| インソース | ChatGPTの導入事例・リスクを知り、生成AI導入の検討材料にできる | 対面/オンライン(公開講座) | 24,400円〜 |
| DMM 生成AI CAMP | 全8レッスンのカリキュラムで生成AI活用時代”に対応する基礎を身につける | オンライン(eラーニング+課題) | 198,000円〜 |
| リスキル | AI研修では、人工知能の全体像について理解し、機械学習やディープラーニング(深層学習)についての知識を深める | 対面/オンライン | 要問い合わせ |
| AVILEN | 実践力や定着を見据えた、アウトプットを重視したプログラム | 対面/オンライン(e-ラーニング+ワークシート) | 11,000円〜 |
| トレノケート | ChatGPTの概要から基本の使い方、使い方のコツや具体的なビジネスでの活用方法まで解説 | 対面/オンライン(講義+ハンズオン演習) | 55,000円〜 |
| インターネット・アカデミー | 自社の業務を想定した演習で、研修後すぐに効果が期待できる | 対面/オンライン | 要問い合わせ |
| Tech Mentor | 3ヶ月で稼げるスキルを身につけられるプログラム | オンライン | 108,364円〜 |
| マナビDX | 様々な事業者がデジタルリテラシーから実践レベルまで幅広い講座を提供 | 対面/オンライン | 要問い合わせ |
バヅクリ株式会社「ムキアイ」
- 特徴1:受講者が夢中になり、自分ごと化できる企画構成
- 特徴2:アクティブラーニングを実現するファシリテーション
- 特徴3:行動変容コミット、受講生同士でアクションプランを約束
| 主なプログラム例 | ChatGPT活用ワークショップ 基礎編 |
| AI研修の特徴 | 業務への活用や効率化のアイデアを得ることをゴールに、ワークを重ねることで使い方を理解 |
| 講師陣の特徴・強み | 営業・IT部門立ち上げ・PMを経て独立、現在はベンチャー創業メンバー兼IT講師として活動する講師が担当。 |
| フォロー体制 | – |
| 研修形式 | 対面/オンライン |
| 料金目安 | 要問い合わせ |
インソース
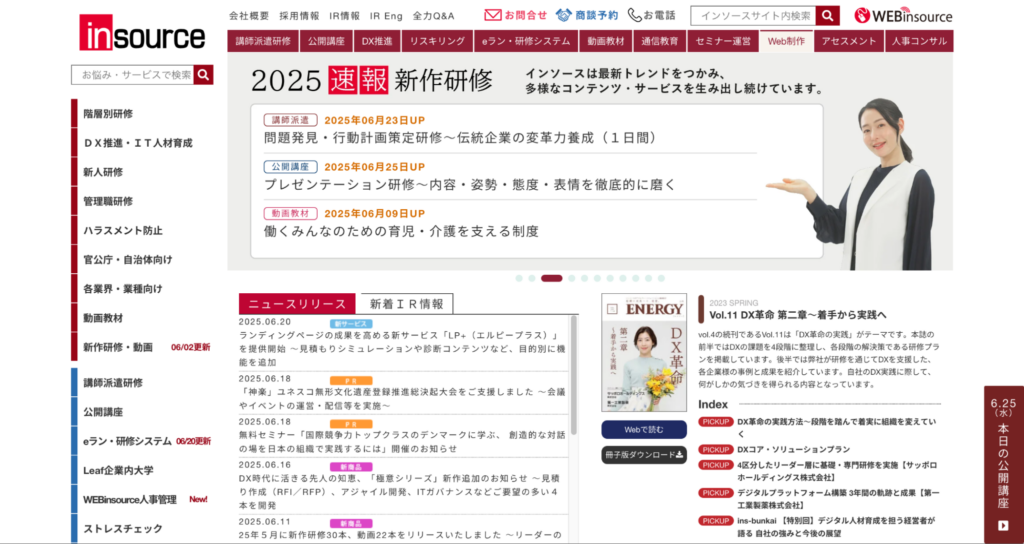
- 特徴1:カスタマイズの柔軟さ
- 特徴2:現場で役立つスキルやノウハウの習得を重視
- 特徴3:研修前後の準備・フォローのサービスやオプションが豊富
| 主なプログラム例 | ChatGPT理解研修~導入事例やリスクを知り、組織での活用方法を検討する |
| AI研修の特徴 | ChatGPTの導入事例・リスクを知り、生成AI導入の検討材料にできる |
| 講師陣の特徴・強み | 年間2,000名以上の応募の中から採用試験を突破した選りすぐりの講師 |
| フォロー体制 | – |
| 研修形式 | 対面/オンライン(公開講座) |
| 料金目安 | 24,400円〜 |
DMM 生成AI CAMP

- 特徴1:目的に応じた学習コースを用意、現場で活かせる技術の習得をサポート
- 特徴2:生成AIの事前知識が全くない人でも現場で使えるスキルが短期間で身につく
| 主なプログラム例 | プロンプトエンジニアリング基礎マスターコース |
| AI研修の特徴 | 全8レッスンのカリキュラムで生成AI活用時代”に対応する基礎を身につける |
| 講師陣の特徴・強み | これまで1000本以上のAI関連記事を執筆するなど、AI業界で幅広く活躍するキーパーソンがカリキュラム監修 |
| フォロー体制 | ・無制限のチャット質問サポート・何度でも課題提出できる・学習進捗の見える化 |
| 研修形式 | オンライン(eラーニング+課題) |
| 料金目安 | 198,000円〜 |
リスキル

- 特徴1:すべての研修が料金一律
- 特徴2:実践的で高品質な研修
- 特徴3:安心の研修準備フルサポート
| 主なプログラム例 | AI研修 【機械学習を活用し、企業内で活かす】 |
| AI研修の特徴 | AI研修では、人工知能の全体像について理解し、機械学習やディープラーニング(深層学習)についての知識を深める |
| 講師陣の特徴・強み | 多数の登壇経験とビジネスの経験を併せ持った講師が講義を担当 |
| フォロー体制 | – |
| 研修形式 | 対面/オンライン |
| 料金目安 | 要問い合わせ |
AVILEN

- 特徴1:全社員〜上級エンジニア向けまで、AI人材育成研修を網羅
- 特徴2:自社に最適な人材育成プログラムを提案
- 特徴3:業界No.1レベルの高品質コンテンツ
| 主なプログラム例 | ChatGPTビジネス研修 |
| AI研修の特徴 | 実践力や定着を見据えた、アウトプットを重視したプログラム |
| 講師陣の特徴・強み | – |
| フォロー体制 | 学習サポートオプションあり |
| 研修形式 | 対面/オンライン(e-ラーニング+ワークシート) |
| 料金目安 | 11,000円〜 |
トレノケート

- 特徴1:新入社員から経営層までの全層をカバー、着実な技術力向上を支援
- 特徴2:人材育成専門30年、実務に活かせるトレーニング
- 特徴3:世界22の国と地域、グローバルITベンダーとのパートナーシップあり
| 主なプログラム例 | ChatGPTで学ぶ生成AIビジネス活用 ~仕事の生産性を高めるAIチャット入門~ |
| AI研修の特徴 | ChatGPTの概要から基本の使い方、使い方のコツや具体的なビジネスでの活用方法まで解説 |
| 講師陣の特徴・強み | テクニカルスキルや専門知識だけではなく、トレーナーとしてのティーチングスキルも兼ね備えた講師陣 |
| フォロー体制 | – |
| 研修形式 | 対面/オンライン(講義+ハンズオン演習) |
| 料金目安 | 55,000円〜 |
インターネット・アカデミー

- 特徴1:開発現場や海外拠点から取り入れた実践的なカリキュラム
- 特徴2:1995年から培われたIT教育のノウハウ
| 主なプログラム例 | 生成AI・ChatGPT研修 |
| AI研修の特徴 | 自社の業務を想定した演習で、研修後すぐに効果が期待できる |
| 講師陣の特徴・強み | 開発現場でノウハウを積んだプロフェッショナルが貴社のIT研修の講師を担当 |
| フォロー体制 | 宿題から研修成果の確認までサポート |
| 研修形式 | 対面/オンライン |
| 料金目安 | 要問い合わせ |
Tech Mentor
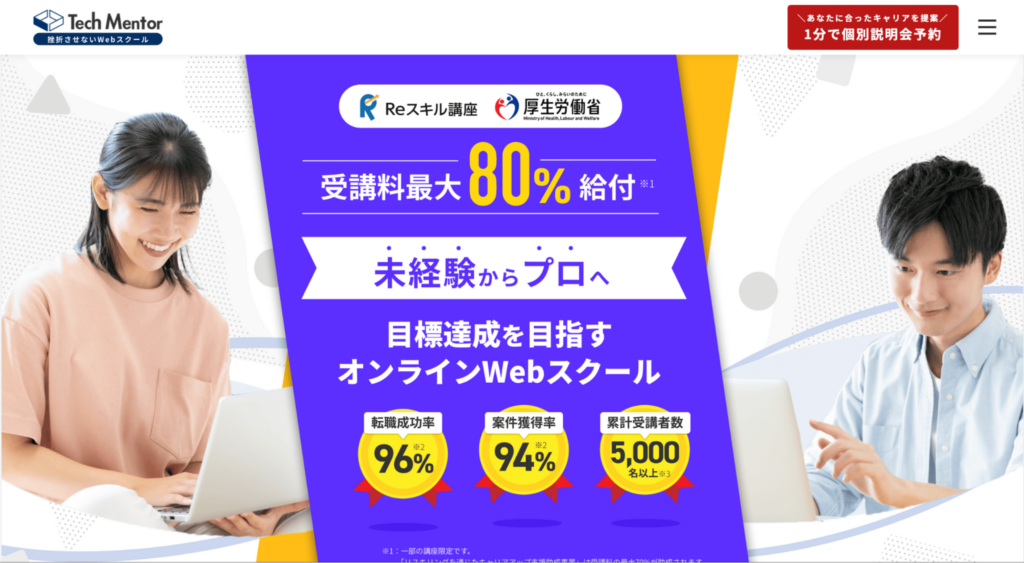
- 特徴1:無駄を削ぎ落とした最短目標達成カリキュラム
- 特徴2:学習の成果物で実績を積み上げる学習課題
- 特徴3:未経験者が9割実践していない効率的勉強法を指南
| 主なプログラム例 | 生成AI活用コース |
| AI研修の特徴 | 3ヶ月で稼げるスキルを身につけられるプログラム |
| 講師陣の特徴・強み | 厳しい選考を通過した現役エンジニア・フリーランスがメンターを担当 |
| フォロー体制 | 専属メンターの1on1フォローあり |
| 研修形式 | オンライン |
| 料金目安 | 108,364円〜 |
マナビDX

- 特徴1:経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) が運営するデジタル人材育成プラットフォーム
- 特徴2:経済産業省・IPAで定めたスキル標準に紐づいた講座を紹介
| 主なプログラム例 | ChatGPT活用研修 |
| AI研修の特徴 | 様々な事業者がデジタルリテラシーから実践レベルまで幅広い講座を提供 |
| 講師陣の特徴・強み | – |
| フォロー体制 | デジタルスキルを学ぶことでの課題や疑問を、AIチューターにチャットで相談できる |
| 研修形式 | 対面/オンライン |
| 料金目安 | 要問い合わせ |
人事担当者が知っておくべき、研修効果を最大化するポイント

全社員向けAI研修の効果を最大化するために、どんなポイントに気をつけるべきなのでしょうか。
研修を「やらされ仕事」にしないための動機付け
受講者の主体性の有無は、A研修の効果を大きく左右します。
「会社に言われたから仕方なくやっている」という受け身の姿勢では、せっかくの投資が無駄になってしまいます。
研修を受けてもらう前に、経営陣などから「なぜAIスキルが必要なのか」を明確に伝えるとともに、「あなたの仕事をより価値あるものにするため」という個人のメリットも具体的に示しましょう。
研修後の実践を促すフォローアップと環境づくり
受講後にAI活用を促すフォローアップも重要です。
受講直後は意欲的でも、実際の業務で躓いた時に質問できる環境がなければ、せっかく学んだスキルが使われなくなってしまいます。
定期的な実践報告会や、AI活用のベストプラクティスを共有する社内コミュニティを構築するなどの取り組みを行い、研修で得た知識の定着・活用を促しましょう。
また、上司自身がAI活用をリードし、部下の実践を積極的に評価・推奨する文化づくりができるとベターです。
まとめ
全社員向けAI研修は、企業競争力維持のための必須投資です。
AIリテラシーという守りの知識と、業務効率化という攻めのスキルの両方を習得することで、組織全体の生産性向上を実現できます。
本記事を参考に自社に合った研修を選択して、「AIを使いこなす組織」への変革を目指しましょう。
仕事と組織の向き合い方を変える
対話型実践研修「ムキアイ」
「研修はやっている。でも現場は変わっていない気がする」「理論は学んだはずなのに、実践ではうまく使えていない」そんなお悩みはありませんか?
バヅクリの対話型実践研修「ムキアイ」は、身につけてほしい力と、現場で本当に使える力を結びつける、理論と実践の“架け橋”となる対話型実践研修です。
職場に“行動の変化”と“関係性の変化”を起こす研修をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。