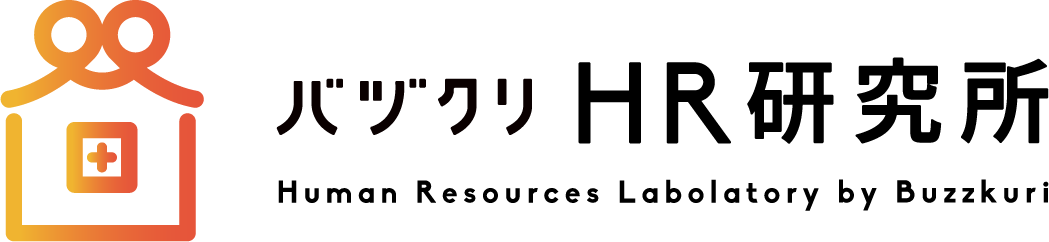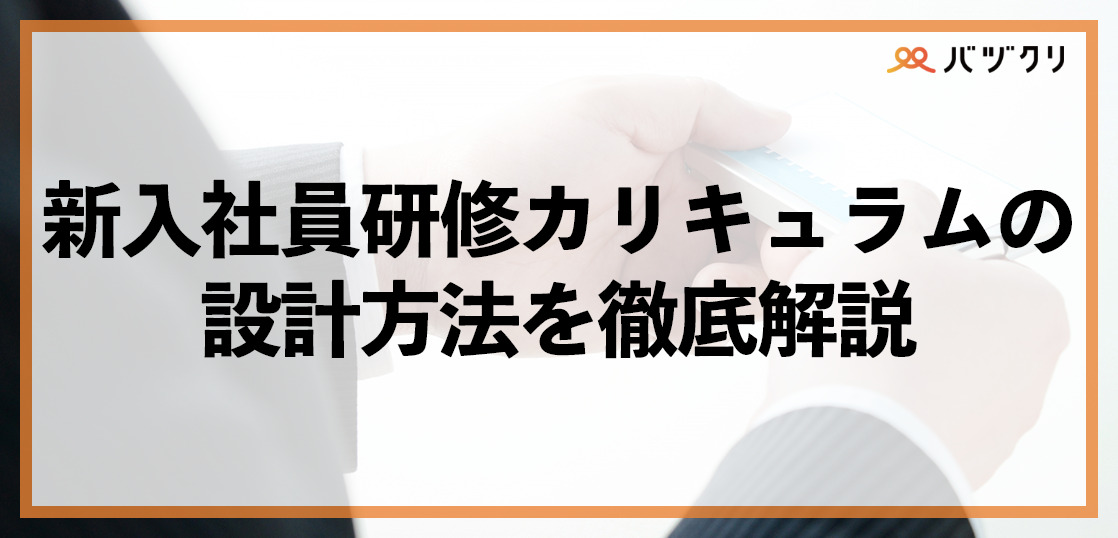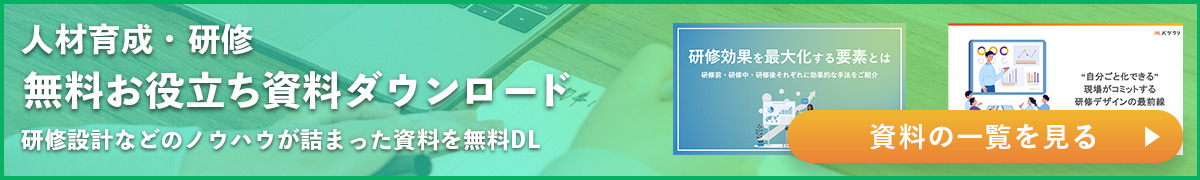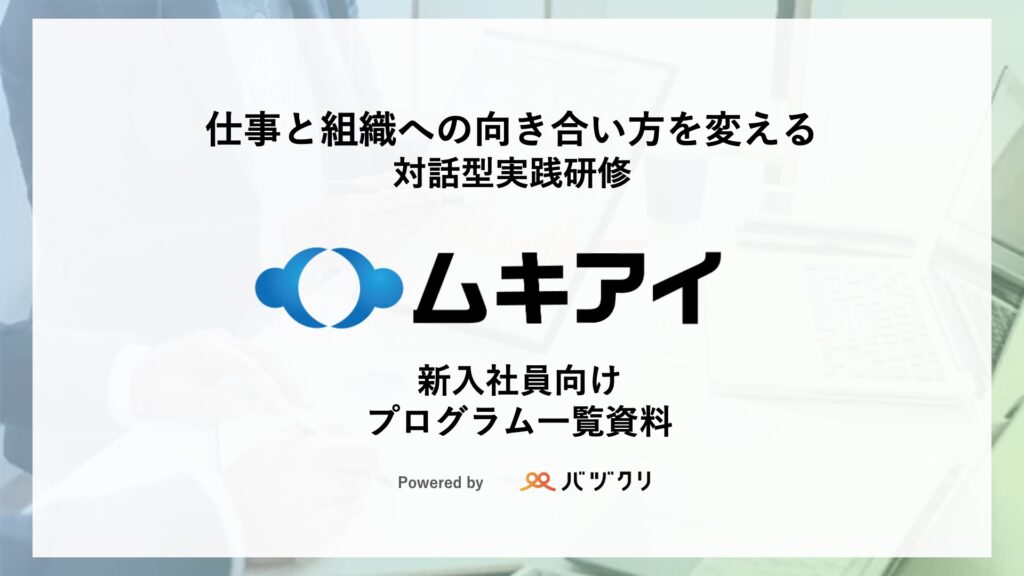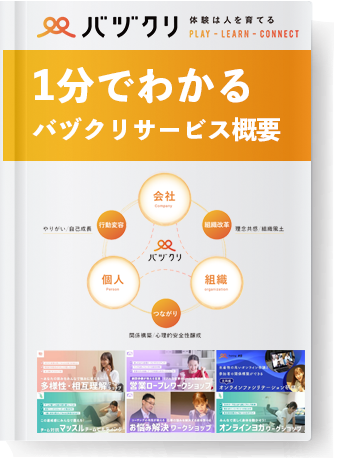新入社員研修は、新入社員が社会人になって1番最初に受ける教育であり、社会人としてのスタートダッシュを切れるかを左右する非常に重要な研修です。
「新入社員研修の間に必ず〇〇を身に付けなければならない」といった厳密なルールは存在しないため、会社ごとにさまざまな研修カリキュラムを取り入れています。
本記事では、一般的な新入社員研修カリキュラムの設計のしかたや研修スケジュールについて、事例をあげながら解説します。初めて人事や研修担当者になった方が、スムーズに新入社員研修の企画運営をできるようまとめていくので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
新入社員研修におすすめのバヅクリ
バヅクリの「ムキアイ」は短時間でも実践的な学びを得られる議論・実践・フィードバック中心のアクティブラーニング研修を提供しています。
新入社員研修に課題をお持ちの方、お困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください。
バヅクリの新入社員におすすめの研修概要は以下からダウンロードできます。
新入社員研修の目的を理解する
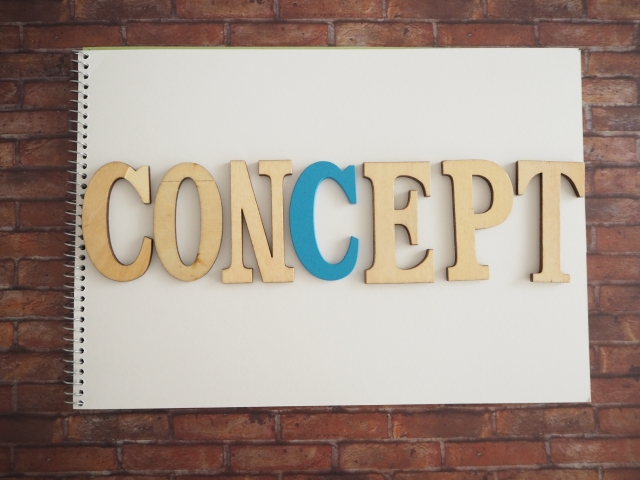
新入社員研修のカリキュラムを考える際は、まず新入社員研修の具体的な目的を理解するところからスタートしましょう。
ここでは、短期的な研修目的と、中長期的な研修目的に分けて解説します。
短期:1~3か月間の目的
新入社員研修は、一般的に入社後から配属までの1か月~3か月の期間をかけて実施されます。
この短期間では、新入社員の即戦力化がもっとも重要な研修目的となるでしょう。
新入社員を即戦力化させるためには、主に一般知識習得や業務スキルの習得、コミュニケーション力の向上などの研修が中心となります。
この、新入社員を即戦力化するという短期目的を分解すると、具体的に以下の短期目的に分けられます。
- 学生と社会人の違いを認識してもらう(マインドセット)
- 早期に社会人としての当事者意識を持ってもらいスタートダッシュを実現する(マインドセット)
- 企業文化や社内ルールなどを理解させ、配属後に業務にスムーズに就けるようにしてもらう(知識・スキル習得)
- 配属後の現場では教育時間を割きにくい事項(一般のビジネスマナーや経済知識など)のインプットをしてもらう(知識・スキル習得) など
中長期:1年~3年間の目的
新入社員が自己学習と成長を継続できる状態をつくることが、中長期的な新入社員研修の目的となります。
入社後の数か月間で、電話応対や名刺交換のビジネスマナーやある程度の業務知識をつけることは可能ですが、新入社員が数年後も成長し続けることは容易ではありません。
新入社員が能動的に自己学習を続け、成長していくことを目的とする場合、新入社員研修のカリキュラムは「仕事のスタンス」「キャリアプランニング」など意識開発研修が有効と言えます。
研修の効果を最大化するために必要な準備とは
「研修をしてもその場限りになってしまい、あまり意味がない」そう感じている人事担当者も多くいらっしゃるのではないでしょうか。でも実は研修に意味がないのではなく、「意味がある研修」にするためには明確な戦略と計画が必要です。
HR研究所では、従業員研修のプログラム設計と実施において、研修前・研修中・研修後の3段階に分け研修の効果を最大限に高める手法をまとめました。
資料は下記からダウンロードできますので、ぜひ従業員研修の計画にお役立てください。

新入社員研修のカリキュラムをつくるうえでの意識したいポイント

続いて、新入社員研修のカリキュラムをつくるうえで意識してほしいポイントについてご紹介します。
新入社員研修の前年実績を確認する
まったくのゼロベースから研修カリキュラムをつくるのは困難です。
まずは、前年の新入社員研修を担当していた社員や、新入社員研修に関わったことのある上司などから情報収集をしましょう。
- 前年はどのような研修を実施したのか
- 当時の研修目的
- 研修の目標と目標の達成可否を判断するKPI
- 研修期間や予算
- 研修対象となった新入社員のデータ
上記情報を集めながら、どのような点が良かったのか、また改善が必要と感じられたのか確認しておくことが大切です。
配属先の現場にヒアリングを行う
新入社員は研修を受けた後は現場に配属になるため、必ず配属先の現場社員に「どのような新入社員に来てほしいのか」「今まで配属された新入社員に関することで何か困りごとはないか」などヒアリングをすることが重要です。
一般的に、新入社員研修は人事部や教育担当、総務部などが主体となって企画運営をします。
人事部の考えだけで研修カリキュラムをつくってしまうと、新入社員が配属先の現場社員の期待レベルに到達せずトラブルが起きる可能性もあるためです。
研修カリキュラムをつくる際は、必ず現場と目線合わせをするよう注意しましょう。
新入社員に身に付けて欲しいスキルをリストアップする
研修カリキュラムをつくる際は、新入社員に身に付けてほしいスキルや知識をなるべく細かく、具体的にリストアップしましょう。
例)
- 名刺交換の方法を覚える
- 電話応対ができるようになる(よく使う敬語も覚えてもらう)
- 社内システムを使って勤怠申請をする方法を覚える
- 日報の書き方を覚える
- 基本的な報連相のしかたを学ぶ
- 社会人としての身だしなみの注意点を把握する
項目は多岐に渡りますが、これらを細かくリストアップすることで、研修カリキュラムがつくりやすくなります。
研修の効果を最大化するために必要な要素とは→無料で資料をダウンロードする
新入社員研修のカリキュラムでよくある内容

本章では、多くの企業で取り入れられている一般的な新入社員研修のカリキュラム内容をご紹介します。
プログラム1:ビジネスマナー研修
ビジネスマナー研修とは、社会人にとって基礎的なマナーを習得するための研修を意味します。
ビジネスマナーは年齢に関係なく共通しており、社会を生きるうえで身につけるべきスキルです。
研修内容は身だしなみや言葉遣いのほかにも、電話対応や名刺交換などが用意されています。
社会経験の少ない新人社員向けに実施されることが多いでしょう。
引用:ITトレンド
おすすめのビジネスマナー研修(2025-2026入社対応)

本格的な社会人デビューを前に最低限のマナーを理解し、お客様はもちろん上司や先輩とのコミュニケーションを円滑に行えるようにするための研修です。
新型コロナの影響で社会人と接してきた経験が乏しく、最低限の一般常識を理解してもらうなど、2025-2026入社の新社会人に対応した内容となっており、学生時代に社会人と接してきた経験不足を補うことができます。
プログラム2:ロジカルシンキング研修
新入社員の論理的思考力を鍛え、合理的かつロジカルに課題解決を行う力を養う研修です。
ロジカルシンキングの力とは、ビジネスでの課題解決のために必要な情報を整理して、自分なりの結論を出すこと。
そして周囲の人たちと合意をとりながら自身の考え・情報を伝達するスキルを指します。
おすすめのロジカルシンキング研修
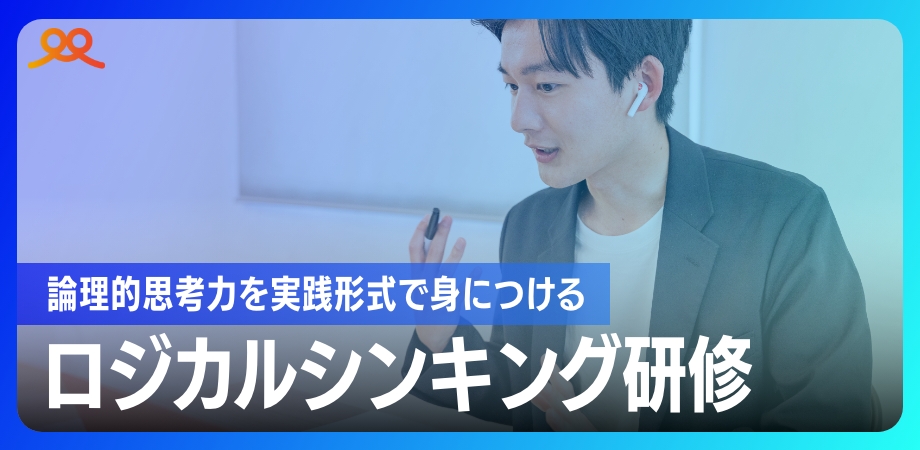
論理的思考について、基礎理論を学習し、自身の業務においてどのように活用するのか考える研修です。ワークを通じて論理的思考を実践し、グループでの議論を通じて自身の思考に関しての気づきを得ながら学習を進めます。
自分の思考の癖や問題点は気づきにくいため、グループワークにより他のメンバーの思考に触れながら、自身の改良点に気づくようなワークとなっています。
プログラム3:コミュニケーション研修
コミュニケーション力とは、自分の考えを相手に伝える発信の能力と、相手の気持ちや考えをくみ取る洞察力、それらを受け取る力の総称です。
自分の考えを社内のメンバーやお客様に分かりやすく伝える、発信のコミュニケーション力を高める研修と、相手の考えを洞察し、正しく解釈する力を養う受動のコミュニケーション力研修があります。
おすすめのコミュニケーション研修
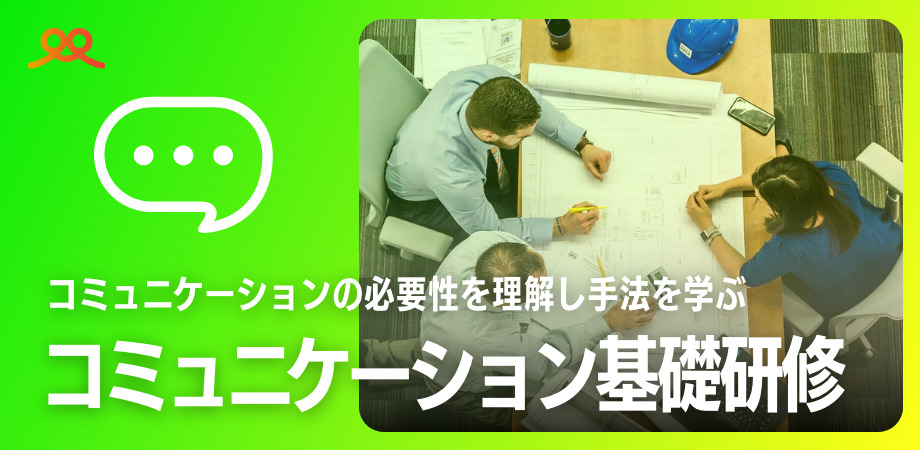
コミュニケーションにおける悩みを「傾聴力」と「質問力」向上で解決します。
- 聴くことの重要性理解
- 信頼関係構築のための聴き方
- 指示の意図汲み取り
- 上手な質問方法
- 雑談力の向上
を目標に、ワーク中心のカリキュラムを実施します。
受講者同士でコミュニケーションの悩みを共有後、聴き方による信頼関係の変化を実践形式で体験。図形描写ワークで指示の伝達難しさを体感し、質問の重要性と効果的な質問方法を学びます。グループワークを通して実践的なスキル習得と受講者同士の交流を促進し、研修後すぐに職場での実践が可能です。
プログラム4:営業基礎研修
営業職に配属される新入社員向けに行われるのが営業基礎研修です。多くの営業職に共通して求められる、次の項目を養成する研修カリキュラムがあります。
- お客様に要件を明確に伝えるプレゼンテーション能力を高める
- 市場調査や企画書作成のしかたを学ぶ研修
- 実践的なロールプレイング研修 など
おすすめの営業基礎研修
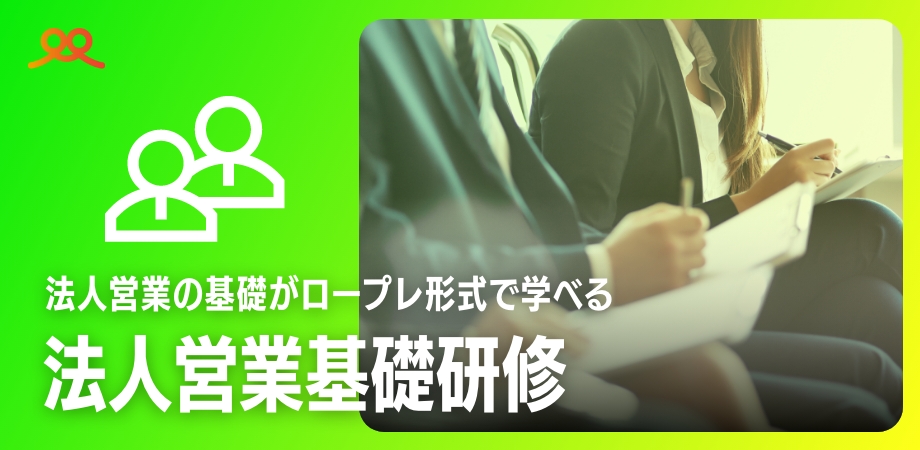
BtoBの営業に必要な基本スキルをワークショップを通して学ぶ研修です。
・顧客との信頼関係を築くために必要なこと
・商談フェーズごとに注力すべきポイント
・顧客ニーズの把握と興味喚起の手法
・顧客のタイプとシチュエーションに応じた提案カスタマイズのポイント
・意思決定のための不安を解消するために留意すべきこと
について、グループワーク形式で実践を交えながら習得します。
プログラム5:その他、ユニークな研修
上記でご紹介した以外にも、ユニークな新入社員研修が多数存在します。
たとえば、国際自動車株式会社で実施されている、都内を35キロも歩いて回るウォーキング研修や、東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランドが一般の企業向けに行うディズニーアカデミー研修などがあります。
新入社員研修のスケジュール、カリキュラムをどうつくっていくのか?

ここからの章では、新入社員研修はどのようなスケジュールで進めていけばいいのか、また研修カリキュラムのつくりかたについて、流れに沿って解説します。
カリキュラムをつくる手順は?
新入社員研修カリキュラムをつくる手順は、以下を参考にしてください。
- 新入社員の特徴や性格などデータを集める
- 経営層だけでなく配属先の現場社員にヒアリングを行う
- 1、2をふまえて、新入社員研修の目的および目標を定める
※この辺りで新入社員に身に付けてほしい項目をリストアップすると良い
- 新入社員研修を実施する期間を決める
- 新入社員研修の予算の大枠を決める
- 新入社員研修の研修講師を誰にするか、外注か内製か決める
- リストアップした項目をもとに、具体的な研修カリキュラムを作成し、同時にスケジュールも組んでいく
上記をふまえると、新入社員研修のカリキュラムを1日で作成するのは難しいでしょう。
実際のカリキュラム作成に入る前に、新入社員研修を企画するためのスケジュールを確保することも大切です。
また、見落としがちですが、研修の効果を最大化させるためには研修自体だけではなく研修前、研修後の設計も重要です。
研修の効果を最大化するために必要な要素とは→無料で資料をダウンロードする
どのようなスケジュールでカリキュラムをつくっていくのか?ポイントは?
新入社員の研修スケジュールを組む際は、社内行事の有無や外部講師のスケジュール、資格受験の日程など、複数のスケジュールを加味しておくことが重要です。
すべての研修を内製化する予定の企業は、まず社内の繁閑期がいつなのか年間スケジュールや社内行事の日時を確認します。
また、配属先の現場社員に、何月何日までに新入社員の人手が必要かヒアリングするのも大切です。
外部の研修会社を利用する予定の企業は、なるべく早めに研修講義の日時や場所、定員人数などを確認します。
ギリギリになって申し込むと、希望の日取りで外部研修が受けられなくなる可能性もあります。
また、人気のあるマナー講師のスケジュールも早めにおさえておくと安心です。
その他にも、配属されるまでに特定の資格受験が必要な職種もあるでしょう。
資格によって、年に1度しか受験できないものもあるため、各年の資格受験日もあらかじめ確認することが大切です。
以上のように、社内外のスケジュールを確認したうえで、自社の研修スケジュールを組むように心掛けましょう。
しかし自社で研修のカリキュラムをすべて組み、実施しようとすると、膨大な工数がかかってしまいます。
そこでおすすめしたいのが、研修サービスの「バヅクリ」の活用です。
バヅクリの「ムキアイ」は研修プログラムの選定のお手伝いから研修当日の運営までまるっとお任せできるので、研修の実施における人事の工数を90%以上削減できます。
新入社員研修でお悩みの場合は、ぜひバヅクリのご活用をご検討ください。
バヅクリのサービス資料をダウンロードする>>
外注する際に役立つサービスはあるか?

新入社員研修は、カリキュラムの作成から丸ごと外注することが可能です。
また、カリキュラムは自社で作成をして、部分的に外部の研修サービスを利用することもできます。
外注のメリット・デメリットや依頼相場
新入社員研修の外注を検討する際は、次のメリット・デメリットがあります。
研修を外注するメリット・デメリット
研修の企画から運営、効果測定までワンストップで提供している研修専門会社を利用すれば、プロによる質の高い研修カリキュラムを企画することができ、人事の手もわずらわせません。
カリキュラムは企画できるけど、実際に教える研修講師がいない場合、研修講師の派遣だけピンポイントで利用することもできる点はメリットと言えます。
一方、外注を利用すると費用が大きくなりやすい点はデメリットです。
また、研修会社・研修講師によっても、合う合わないがあるため、100%外注が安全とは言い切れません。
研修を内製するメリット・デメリット
研修を内製することのメリットは、コストをおさえつつ自社に研修教育のノウハウを蓄積できる点と言えます。
研修の企画から実施、実施後の効果検証まで社内のリソースで対応することで、なにかトラブルや疑問点があった際も、すぐに確認できるのは利点でしょう。
一方、研修を内製する場合、非常に時間がかかる点はデメリットです。
新入社員研修のカリキュラム作成の際は、毎年の新入社員の動向や、現場での課題感、同業他社でどのような研修を取り入れているのかトレンド調査など、さまざまな情報を専門的にまとめるスキルが求められます。
一般的に、人事部や総務部、研修担当者が主体となって新入社員研修を企画運営しますが、そこまで人的リソースを割けない企業が大多数でしょう。
どんな外注サービスがあるのか?
最後に、どのような研修外注サービスがあるのか、実例を3つ取り上げてご紹介します。
1. オンラインの研修サービス
コロナ禍以降、テレワークが定着した昨今では、新入社員研修をオンラインで実施する企業も増加しました。
テレワーク下でも質の高い新入社員研修が実施できるように、新入社員1人あたり1000円~2000円前後の価格で、数千種類の講座が受け放題になるサービスがあります。
その他にも、バヅクリ株式会社が提供する研修サービス「バヅクリ」のように、オンラインでもチームの「アクティブラーニング」「行動変容」「チームビルディング」の3つをコンセプトに開発された独自のプログラムを提供するサービスもあります。
新入社員だけでなく、中途社員向けの研修としても活用できる点が魅力的です。
バヅクリ株式会社「バヅクリ」

2. 講師派遣型や公開型の研修サービス
多くの人材会社や研修サービス会社が提供しているのが、講師派遣や講義の一般公開型の研修サービスです。
日程は、1日で完結するのから、数週間かけて実施するものまで幅広いです。
新入社員1人あたり3万円~5万円の費用が相場となっており、Web・紙ともに研修教材に力を入れているサービスもあります。
3. 職種や特定スキルに特化型の研修サービス
営業職、エンジニア職など特定の職種に特化して、専門的に展開している研修サービスがあります。
たとえば、営業職ならではの提案スキルやヒアリング力、プレゼンスキルや営業行動の習慣化などピンポイントで学ぶことが可能な研修です。
自社で行うビジネスマナー研修や、ロジカルシンキング研修などにプラスして組み合わせることもできます。
自社の新入社員が一般職や総合職だったとしても、IT・Webに関する最低限の知識を習得するために、スポットで外注サービスを利用できるのは便利でしょう。
新人研修カリキュラムの例

それでは、実際に企業がどのようなカリキュラムで新人研修を行なっているか、例をご紹介します。
1. 株式会社サニーサイドアップグループ
PRやマーケティング関連の事業を行う同社は、新入社員同士の繋がり作りだけでなく、先輩社員などとのタテやナナメの繋がりを作ることを目的とし
などのカリキュラムを、のバヅクリを利用し実施しました。
主にリモートワークで業務を行っていた同社はメンバーから、「OJTに入った際に、初対面の新入社員に仕事を教えるのは難しい」との声があったため、その解決のために取り入れたプログラムですが、密にコミュニケーションを取る機会を作り出すことができました。
実施方法はオンラインです。
参考:新入社員同士だけでなく役員・先輩社員ともプログラムを一緒に行うことで生まれる安心感
バヅクリ
2. ソニー銀行
ソニー銀行は、インターネットを活用した個人のための資産運用銀行として誕生した銀行です。
同社では
- ビジネスマナー / コミュニケーション
- 銀行知識 / 財務知識など
- 企業理解
- モチベーション向上
の4つを軸として新入社員研修のカリキュラムを作成しています。
詳しい内容としては、「オフィスツアー」、「部署インタビュー」、データドリブンな企業文化を目指した「データサイエンスブートキャンプ」、「キャリアプランニング研修」などを実施しています。
「データドリブンな企業文化」をめざして新入社員研修にデータサイエンスの集中講座を組み込む
参労総合研究所
3. ヤマハ株式会社
楽器・音響機器・ネットワーク機器の製造販売などを行う同社は、入社1年目、2年目、3 年目それぞれ入社時期に分けて目標を定め、新入研修を行っています。
1年目はビジネスマナーの習得や企業理解を深める、マインドセットなどを主に研修を実施し、研修で学んだ後にOJTで実践しアウトプットを行いながらさらに学びを深めます。
研修のゴールを明確にしプログラム内容を取捨したり、座学中心であった今までの研修プログラムの見直しを行ったりしています。
明確なゴールとロードマップを定め、研修内容を整理・刷新インプットとアウトプット、効果測定を繰り返して目標をめざす
参労総合研究所
まとめ

新入社員研修のカリキュラムは、短期的また中長期的な目的を意識しながら、関係者スケジュールを加味して作成することが大切です。
研修カリキュラムをつくるのが難しい場合や、社内に研修講師の人材が不足している場合は、バランス良く外部の研修サービスの利用を検討してみてください。
人事工数を90%以上削減できる新入社員研修

研修プログラム選定のお手伝いから研修当日の運営まで、まるっとお任せできるので、人事工数を90%以上削減できます。
また、通常の座学の研修とは異なり、新入社員同士の議論、実践、フィードバック等のアクティブラーニングを取り入れた研修で、学習定着率を高めることが可能です。